小児は、身体機能の未熟さや感染症へのかかりやすさなどから、発熱が起きるのもめずらしくありません。しかし、発熱のある患児と関わるなかで「解熱剤はいつ使えばいいの?」「なかなか熱が下がらずどうしよう」などと困った経験はありませんか。
この記事では、小児の発熱のメカニズム、原因、随伴症状、治療、看護計画について詳しく解説します。
小児看護に携わる方は、ぜひご覧ください。
発熱のメカニズムと種類
発熱の定義、メカニズム、種類について解説します。
発熱とは
発熱とは、さまざまな原因によって脳の視床下部にある「体温調節中枢」が刺激されたり、発熱物質が作られたりすることで、体温が正常よりも高くなった状態のことをいいます。
一方、体温中枢機能には異常がないものの、熱の放散が妨げられて体内に熱がこもったままになる状態のことは「うつ熱」と呼び、これも発熱に含まれます。
体温調節中枢には、体温をおおよそ37℃前後に調節する働きがあり、暑い時には発汗を促して体温を下げ、寒い時には筋収縮により熱産生を促しています。体温が高くなりすぎても、反対に低くなりすぎても、身体機能に支障をきたすのです。
小児のなかでもとくに乳幼児では、以下のふたつの理由により、発熱がみられやすいといえます。
- 環境温による影響を受けやすい
- 体温調節機構が未熟であり体温が上昇しやすい
小児の体温(腋窩温)の基準値の目安は以下のとおりですが、平常時であっても個人差が大きいので、一つの目安として考えましょう。
| 新生児期 | 37.1℃ |
| 乳児期 | 37.1℃ |
| 幼児期 | 37.0℃ |
| 学童期 | 36.9℃ |
| 思春期 | 36.8℃ |
乳幼児で37.5℃以上あっても、こどもが元気で、食欲があり、様子が普段と変わらない場合は「平熱」と捉えられますが、気道症状や消化器症状があれば「病的発熱」と捉えられます。
発熱の意義
発熱は、よいイメージをもたれないでしょう。しかし、発熱は身体の防御反応であり、免疫細胞の活性化や病原体増殖の抑制のためには大切なのです。
発熱があることで、体内ではウイルスや細菌と戦うための環境が整えられています。
適切に対処しながら、体の回復を助けることが大切です。
発熱の種類
発熱には「微熱」「中等熱」「高熱」があります。
- 微熱:37.6℃~37.9℃、または平熱と比較して1.0℃以内の上昇
- 中等熱:38.0℃~38.9℃
- 高熱:39℃以上
発熱から解熱までのメカニズム
発熱から解熱するまでの過程には「発熱上昇期」「高温停滞期」「解熱期」があります。各過程において体内で起きていることと、こどもにみられる症状についてまとめました。
| 体内で起きていること | こどもにみられる症状 | |
| 発熱上昇期 | 発熱物質が産生され、体温調節中枢が刺激される。正常より高い温度レベル(セットポイント)で体温が上昇する | 悪寒、震え、四肢末梢冷感の出現 活気の低下 寒さを訴える |
| 高温停滞期 | 熱産生の促進と熱放散の抑制により体温が上昇し、セットポイントで維持される | 倦怠感が強くぐったりする 四肢末梢まで温かくなる 熱さを訴える |
| 解熱期 | 体温調節中枢の設定温度が下がり、熱が放出され、解熱する | 発汗 活気の回復 |
熱型の種類
疾患によって体温の経時的変化が特有のパターンを示すことがあり、これを熱型(ねっけい)といいます。
近年では抗
| 特徴 | 考えられる疾患 | |
| 稽留熱(けいりゅうねつ) | 体温が持続的に上昇し、1日の体温差が1℃以内 | 肺炎、髄膜炎など |
| 弛張熱(しちょうねつ) | 1日の体温差が1℃以上あり、低い時でも平熱までは下がらない | ウイルス感染症、悪性腫瘍、結核など |
| 間欠熱(かんけつねつ) | 日内変動が1℃以上で、とくに周期性はみられない | 腫瘍、マラリアなど |
| 二峰熱(にほうねつ) | 数日の発熱を経て平熱に戻るが、再び上昇し、後に解熱する | 胆道閉鎖症、脊髄障害、ホジキン病、回帰熱など |
小児の発熱のおもな原因
小児の発熱のおもな原因は以下の4つに分けられます。
- 発熱物質によるもの
- 体温調節中枢の障害によるもの(中枢性発熱)
- 熱放散の妨げによるもの(うつ熱)
- 心因的な原因によるもの(心因性発熱)
それぞれの具体的な疾患名は、以下の表のとおりです。
| 具体的な疾患名 | |
| 発熱物質によるもの | 感染症、膠原病、熱傷、悪性腫瘍、甲状腺機能亢進症など |
| 中枢性発熱 | 脳出血、脳腫瘍、頭蓋骨骨折など |
| うつ熱 | 着せすぎ・布団のかけすぎ、熱中症など |
| 心因性発熱 | 機能性高体温症など |
小児の発熱にみられる随伴症状
小児の発熱時には、以下のような随伴症状がみられることがあります。
| 基礎代謝の亢進による変化 | 熱感、発汗、倦怠感 など |
| 細胞内代謝の亢進 | 脱水、脱水による症状 |
| 循環器系の変化 | 心拍数・脈拍数の増加、心悸亢進、血流速度の上昇、血圧低下 など |
| 呼吸器系の変化 | 呼吸促拍、呼吸困難 など |
| 消化機能の低下 | 食欲不振、嘔気、嘔吐、便秘、下痢 など |
| 中枢神経機能障害 | 頭重感、頭痛、めまい、嘔気、嘔吐など |
| 精神的な変化 | 不安、苦痛 など |
随伴症状は、発熱の原因によっても異なります。呼吸器感染症であれば呼吸器系の症状が、消化器感染症であれば消化器系の症状が、発熱時や発熱の前後にみられることがあります。
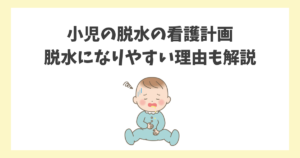
小児の発熱のアセスメント
発熱がある場合、発熱の程度、パターン、随伴症状、原因などについてよく観察し、アセスメントすることが大切です。
アセスメント項目は以下の表のとおりです。
| 基礎的情報 | ・年齢 ・熱性けいれんの既往歴、最終発作時期、発熱時の対応 ・感染症発症者との接触歴 ・予防接種の接種状況 |
| 全身状態 | ・活気 ・表情、活気 ・食欲 ・バイタルサイン ・脱水症状の有無と程度 |
| デバイス・処置 | ・点滴刺入部、ドレーン刺入部の感染兆候 ・ドレーンの排液量、性状 ・膀胱留置カテーテルの疼痛、尿性状 ・穿刺部の感染兆候(骨髄穿刺、腰椎穿刺など) ・手術創の感染兆候 |
| 発熱の特徴 | ・発熱の推移 ・熱型 |
| 随伴症状 | 上の見出し「発熱の随伴症状」参照 |
| 検査データ | ・血液検査:白血球数、CRP、赤血球数など ・尿検査:尿性状、尿タンパク、尿潜血など ・胸部X線検査:肺炎像、心拡大など |
| 環境 | ・衣服 ・室温 |
 ナースもも
ナースもも熱性けいれんの既往がある場合、発熱に伴ってけいれんが起こる可能性があります。最終発作時期や、発熱時の抗けいれん薬使用の指示などについて確認しましょう。既往がない場合でも、初めてけいれんを起こす可能性もあります。
小児の発熱の看護3つのポイント


小児の発熱時の3つのポイントは以下のとおりです。
- 安静の保持
- 苦痛の緩和
- 脱水の予防
ひとつずつみていきましょう。
安静の保持
発熱時には、体力を消耗します。身体の回復を促進するためには、体力の消耗を最小限にする必要があります。
家族へ協力を依頼し、休息時間の確保し、ベッド上での遊びを工夫しましょう。
絵本・読書・シール遊び・DVDやテレビ視聴・ごっこ遊び など
日常生活動作についても、発熱時には動作による負担を軽減させる必要があります。入浴は体温の変動が大きく負担になるため、ベッド上で全身清拭・陰部洗浄をおこないましょう。
トイレまでの移動は倦怠感やそのほかの随伴症状の程度によって判断することが大切です。必要に応じて、ポータブルトイレや尿瓶などを使用しましょう。
苦痛の緩和
発熱や随伴症状による苦痛を緩和しましょう。
ただし、単に熱を下げたり、温めたり、冷やしたりするのでは効果的でないばかりか、症状が悪化する可能性さえあります。ケアのタイミングに注意が必要です。
苦痛緩和のためのケアと、具体的なポイントは以下のとおりです。
| 解熱剤の投与 | ・医師の指示に従って使用する ・用法容量を守る(1日の使用回数上限、間隔など) ・食事前、就寝前などに効果が得られるように投与時間を工夫する(効果持続時間は4~6時間程度) ・活気や機嫌が良好であれば無理に使用する必要はない ・平熱に下げることを意識しなくてもよい |
| 保温 | ・悪寒戦慄、寒気、末梢冷感がある場合は、衣服や掛け物で保温する ・体温が上昇しきって手足が温かくなったら冷罨法へ変更する |
| 冷罨法 | ・悪寒があるうちは実施しない ・末梢冷感が消失し全身の熱感が強くなってからおこなうと、熱の放散に効果的 ・頭部、腋窩、鼠径部、頸部など大きな動脈がある部位を冷却する |



いわゆる「冷えピタ」などの冷却シートを用いる場合は、剥がれたシートの誤飲や窒息に注意が必要です。年少児には控えた方がよいでしょう。
脱水の予防
発熱時には代謝が亢進するため、体内の水分が失われやすくなります。小児は成人よりも脱水になりやすい特徴があり、発熱時にはとくに注意が必要です。
飲水や食事がすすまない場合でも、少量ずつこまめに与えましょう。水分だけでなく、果汁ジュースやゼリーなどで糖分もあわせて摂取できるとなおよいです。
下痢や嘔吐がある場合も、少量ずつこまめに飲水を促します。患児が欲しがっても、一気に多量に摂取するのはひかえましょう。症状悪化の原因となります。
小児の発熱の看護計画
小児の発熱時の看護計画をご紹介します。
看護問題
発熱による苦痛がある
看護目標
解熱し食欲や活気が普段通りになる
OP(観察)
- 体温、発熱のタイミング、持続期間
- 活気
- 機嫌
- 食欲
- 食事摂取量
- 水分摂取量
- 排尿回数、尿性状
- 排便回数、便性状
- 随伴症状の有無と程度
- 脱水症状の有無と程度
- 意識レベル
- 四肢末梢冷感
- 体熱感
- 表情、言動
- 点滴の固定状況
- 点滴刺入部の腫脹や疼痛の有無
TP(ケア)
- 悪寒や冷感がある場合は保温を、悪寒や冷感がなくなれば冷罨法をおこなう
- 医師の指示のもと、解熱剤を投与する
- 発汗による不快感の除去や皮膚の保護のため、全身清拭と陰部洗浄をおこなう
- 水分の摂取を促す
- 医師の指示の範囲内で、好みのものや食べやすいものを摂取してもらう
- 点滴の管理を適切におこなう
- 休息できるよう、ケアや観察のタイミングを工夫する
- ベッド上の遊びを工夫する
- 処方されている薬があれば確実に投与する
- 内服薬がある場合は少量の水に溶いて負担なく内服できるよう支援する
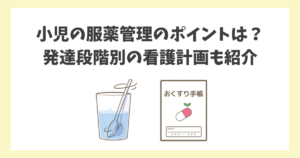
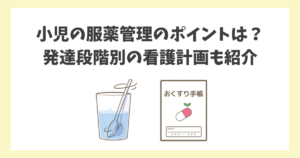
EP(教育)
- 安静の必要性を指導し理解を得る
- 解熱剤の使用方法について指導し理解を得る
- 「寒い時は保温」「熱い時は冷却」するよう指導する
- 水分摂取の必要性について指導し理解を得る
- けいれんを起こしたらすぐにナースコールで知らせてもらう
- 冷却シートの誤飲のリスクを説明する
まとめ
この記事では、小児の発熱の特徴、メカニズム、随伴症状、看護について解説しました。
小児の発熱にはさまざまな原因があり、その原因によって随伴症状も異なります。患児の状態を都度アセスメントし、適切なケアを提供しましょう。
看護計画はあくもあでも一例です。疾患や患児の状態によって内容をアレンジし、看護に役立てていただけたら幸いです。
参考文献
- 日本臨床免疫学会会誌(Vol.35 No6)「小児期のリウマチ性疾患にみる発熱」
- 医学書院「専門分野Ⅱ小児看護学概論 小児臨床看護総論」 第13版
- 照林社「母性・小児看護ぜんぶガイド」古川亮子・市江和子著


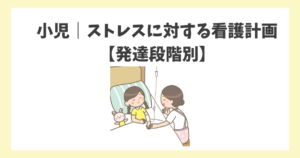
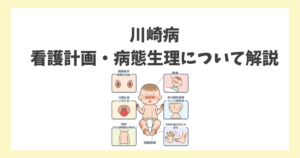

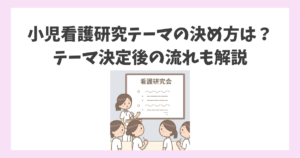

コメント