「小児の脱水はどのような特徴があるの?」「成人と違うの?」このような疑問を抱く新人看護師の方や、看護学生の方がいるのではないでしょうか。
脱水とは、体内の水分や電解質が不足した状態のことです。体から失われる水分量が増えたときや、水分の摂取量が不足しているときに生じます。
小児の脱水には成人とは異なるポイントがあり、小児科ナースとしてこどもと関わる方はおさえておくべき内容です。
この記事では、以下の4つについて解説しています。
- 小児が脱水になりやすい理由
- 重症度の見分け方
- 看護ケアのポイント
- 看護計画
小児看護に携わる方は、ぜひ参考にしてください。
小児が脱水になりやすい5つの理由
小児が脱水になりやすいのには、5つの理由があります。
- 身体に占める水分量の割合が高い
- 体重あたりの必要水分量と不感蒸泄が多い
- 腎機能が未熟である
- 脱水につながる疾患に罹りやすい
- 口渇を感じたり、訴えたりする能力が未熟である
ひとつずつ解説します。
身体に占める水分量の割合が高い
小児は成人と比べて体内の水分量の割合が高いです。年少児になればなるほどその傾向が強く、脱水のリスクが高まります。年齢・発達段階別の、身体に占める水分量の割合は以下の表のとおりです。
| 新生児 | 約75~80% |
| 乳児 | 約70% |
| 幼児 | 約60% |
| 学童から成人 | 約50~60% |
とくに新生児や乳児では、身体に占める水分量の割合が高いため、わずかな水分喪失でも脱水を起こすリスクがあります。
体重あたりの必要水分量と不感蒸泄が多い
小児は体重当たりの必要水分量と不感蒸泄が多いため、INOUTバランスが崩れやすい特徴があります。
体重1kgあたりに1日の必要水分量は以下の表のとおりです。
| 新生児 | 80~100ml/kg |
| 乳児 | 120~150ml/kg |
| 幼児 | 100~120ml/kg |
| 学童 | 60~80ml/kg |
| 成人 | 40~50ml/kg |
参考「家庭の医学WEB版」
また、不感蒸泄量が多いのには、体表面積が関係しています。成人の不感蒸泄量が約10ml/kg/日であるのに対し、新生児は約30ml/kg/日にも及びます。
とくに、発熱時にはたった1℃の体温上昇で、水分喪失量が10~15%程度増加するとされているため、脱水のリスクが高まります。発熱や下痢・嘔吐がなくても、ミルクや母乳の不足、ミルクの不適切な濃度管理によって脱水になることもあります。
腎機能が未熟である
小児の身体機能は成熟しきっていません。腎機能も未熟であり体液量を調整する能力が低いことも、小児が脱水を起こしやすい理由のひとつです。
体液量を調整する能力には、おもに2つあります。
- 尿の濃縮能力
- ナトリウム(Na)の調整能力
これらの機能の低さに加え、脱水時に起こる身体のなかの反応も弱いとされています。成人の場合脱水時には抗利尿ホルモンを分泌し尿の排出をおさえることで、体液量を維持しようとします。しかし、小児の場合はこの調節機構が未熟であり、容易に脱水が進行するのです。
脱水につながる疾患に罹りやすい
小児は、「ノロウイルス感染症」「ロタウイルス感染症」「インフルエンザ」など、脱水を起こしやすい疾患にかかることが少なくありません。
下痢や嘔吐による水分の大量な喪失や、発熱による不感蒸泄量の増加、経口摂取量の低下によって、脱水を起こしやすい状態です。
口渇を感じる・訴える能力が未熟である
小児は、口渇を自覚する能力も未熟です。また、自分自身で水分を摂取する能力が不十分であることも重なって、脱水になりやすいといえます。
小児の脱水の症状
脱水では、以下の症状がみられます。
- 活気の低下
- 皮膚乾燥
- 大泉門や眼窩の陥没
- ツルゴールの低下
- 尿量減少
- 泣いても涙が出ない など
症状は、脱水の程度によっても異なります。
| 症状 | 軽度 | 中等度 | 重度 |
|---|---|---|---|
| 体重減少 | 乳児:5%未満 年長児:3%未満 | 乳児:5~10% 年長児:3~9% | 乳児:10%以上 年長児:9%以上 |
| 意識・神経症状 | 正常 | 傾眠または興奮 | 昏睡 |
| ツルゴール | 2~3秒 | 3~4秒 | 4秒以上 |
| 四肢冷感 | 少しひんやり | ひんやり | 冷たい |
| 口唇・舌 | 湿っている | 乾燥 | 乾燥しきっている |
| 循環状態 脈 血圧 | 正常 正常 | 正常より速い 正常か低下 | 弱く、速い 低下 |
| 尿量 | やや減少 | 減少 | ほとんどなし |
| 啼泣時の涙 | あり | 少し出る | 出ない |
| 大泉門 | 平坦 | 陥没 | 著明に陥没 |
参考「発達段階からみた小児看護過程+関連図第2版 脱水」医学書院 をもとに作成
小児の脱水の検査データ
脱水時の血液・尿・血液浸透圧・酸塩基平衡についてそれぞれ解説します。
血液検査
- 血清ナトリウム(Na):高張性脱水で上昇、低張性脱水で低下
- 血清カリウム(K):下痢で低下、腎不全や代謝性アシド―シスで上昇
- 尿素窒素(BUN):上昇
- クレアチニン(Cre):上昇
尿検査
- 尿比重:上昇
- 尿浸透圧:上昇
- 尿量:減少
血液浸透圧(mOsm/kg/H2O)
- 高張性脱水:300以上 上昇
- 等張性脱水:270~300
- 低張性脱水:270未満 低下
酸塩基平衡
血液の酸性・アルカリ性のバランスは、炭酸(H2CO3)と、重炭酸イオン(HCO3-)によって調整されています。
- 下痢:代謝性アシドーシス 重炭酸イオン(HCO3-)が失われる
- 過換気:呼吸性アルカローシス CO2が体外へ出すぎる
小児の脱水の治療

治療は、年齢や体格、脱水の種類や程度によって決定されます。基本は、経口補水療法または輸液療法による、水分や電解質の補充です。
経口補水療法
医療用の内服電解質剤:ソリタT顆粒や、市販の乳幼児イオン飲料:OS-1などを用いておこないます。スポーツ飲料は、塩分の含有量が低く、消化管を刺激する成分が含まれていることがあるため、それだけで水分補給をおこなうのにはリスクをともないます。
水分は、一度に多く飲むと嘔吐や下痢を誘発することがあるため、少量頻回投与とします。スプーン1杯程度から開始し、様子を見ながら徐々に量を増やしていきます。

母乳のみを摂取している乳児の場合は、母乳を継続しましょう。母乳には水分と電解質が豊富に含まれています。人工乳は控えた方がよいケースもあるため、医師の指示にしたがいましょう。
輸液療法
輸液療法では、血管に直接水分を補給できるため、中等度~重度の脱水で血液循環の改善が急がれる場合に選択されます。輸液の種類は、脱水の種類によって異なりますが、開始時には生理食塩液や酢酸リンゲル液が選択されることがほとんどです。
小児の脱水の看護ケア

小児の脱水に対する看護ケアのポイントは、以下のつです
- 脱水症状の観察とアセスメント
- 治療のサポート
軽度~中等度の脱水では、外来で経口補水療法や短時間の輸液療法で症状がよくなることがあります。経口補水療法は、症状をみながら徐々に進めていくのがポイントです。
中等度~重度の脱水では、入院管理が必要になるケースが多いです。輸液療法で初期治療をしながら、徐々に経口摂取をすすめていくことになります。適切な点滴管理によって、治療が確実におこなわれるようサポートしましょう。
輸液は、医師の指示の速度で投与します。急速に投与すると、

慣れない人(看護師や医師)から突然飲水をすすめられたり、痛い思いをして点滴を挿入されたりと、多くの患児は戸惑います。看護師には、発達段階に合わせたわかりやすい説明が求められます。
小児の脱水の看護計画
脱水時には「体液量不足による脱水のリスク」や「循環血液量の減少に関連するショックのリスク」「電解質バランスの乱れ」など、病態によってさまざまな看護問題がつきます。
今回は、感染性腸炎による嘔吐と下痢がある想定で、「体液量不足による脱水のリスク」をあげ、看護計画を立案してみましょう。
看護問題
体液量不足による脱水のリスク

NANDAだと「体液バランス異常」との診断になります。
看護目標
- 治療により適切な水分補給がおこなわれ、尿量が正常に回復する(1ml/kg/hr 以上)
- 脱水の進行が防がれ、バイタルサインが安定する
OP(観察項目)
- バイタルサイン
- 活気
- 機嫌
- 下痢と嘔吐の頻度と程度
- 意識障害の有無
- 四肢末端の冷汗と色調
- ツルゴール反応
- 尿量、尿回数
- 水分摂取状況
- 皮膚・口唇・舌の乾燥の程度
- 口渇感
- 啼泣時に涙がみられるか
- 乳幼児(~1歳半ころ)の場合、大泉門の陥没の有無と程度
- 点滴刺入部に、発赤、腫脹、疼痛、硬結、漏れがないか
- 経口補水療法や点滴への受け入れ
- 食欲
ツルゴール反応:皮膚の弾力性の評価。皮膚をつまみ、戻るまでの時間が長いほど、脱水が強いサイン。
TP(ケア)
- 輸液を確実におこなう。点滴への受け入れが悪い場合は、保護ガーゼなどで覆い、恐怖心を和らげる。好きなキャラクターの絵を描いたり、シールを貼ったりすると効果的。
- 下痢や嘔吐がみられたら、適切に処理する
- バイタルサインの変化や症状の悪化があれば医師へ報告する
- 経口摂取が許可されている場合、少しずつ水分摂取をうながす。糖分が多いジュース類や牛乳などの摂取は、下痢の悪化につながりやすいため、控える。
- 食欲がある場合、消化によいものを少しずつ摂取してもらう。基本的には病院食のみとし、医師から許可があれば持参したゼリーを摂取してもよい
- 口唇が乾燥している場合は、ワセリンやリップクリームで保護する

経口補水療法のみの場合は、低血糖にも注意が必要です。水やお茶ばかりを飲ませるのではなく、イオン飲料やリンゴジュースなどで、糖分の補給も忘れずに!
EP(教育)
- 水分摂取の必要性を説明し、理解を得る
- 経口補水療法のすすめかたを説明し、理解を得る
- 点滴の必要性と重要性を説明し、理解を得る
- 牛乳や乳飲料、糖分の多いジュース、炭酸飲料を控えるよう説明する
- 点滴を痛がる様子があれば教えてもらう
まとめ
今回は、小児の脱水について解説しました。
- 小児は脱水をきたしやすい
- 小児の脱水は悪化しやすい
- 経口補水療法および輸液療法を適切におこなうことが重要
小児の脱水の看護ケアのポイントを理解し、患児の年齢や理解度、疾患に合ったケアを提供していきましょう。

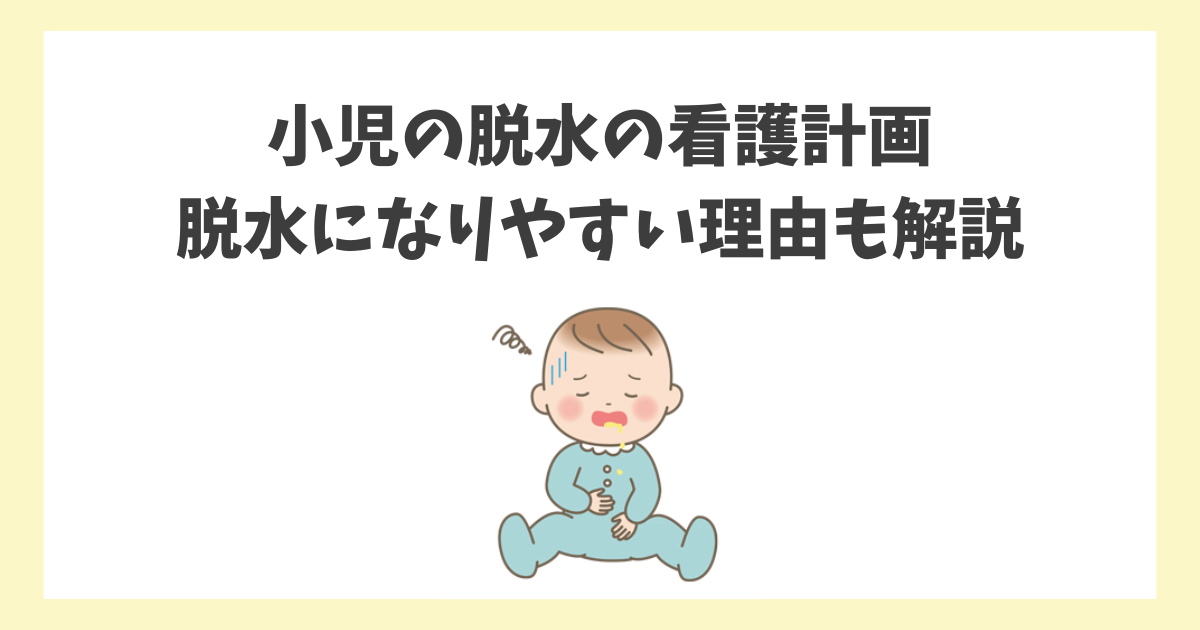
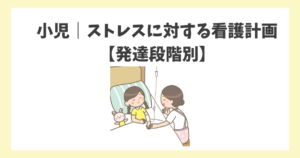
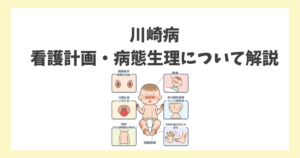
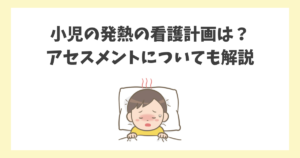


コメント