小児の転倒・転落予防策や、事故発生時の対応について、看護計画の立案方法や実際の対応方法がわからずに悩んでいませんか。
小児は成長や発達にともなって動きが活発になり、思わぬ転倒や転落のリスクがあります。入院中はとくに、慣れない環境での生活や、行動範囲の制限などによって事故が発生しやすく、看護師や保護者にとって大きな心配の種となります。
そこで今回は、小児の転倒・転落の特徴、予防策、看護計画、事故発生時の対応について詳しく解説します。大切な子どもたちが安全な療養生活を過ごせるよう、適切な対策を考えてみましょう。
小児の転倒・転落の特徴
小児の転倒・転落の特徴は、発達段階によって異なります。乳児期・幼児期・学童期それぞれの特徴についてみていきましょう。
乳児の転倒・転落の特徴
乳児期には、身体機能の著しい発達がみられます。しかし、危険の察知や回避能力が乏しいため、転倒や転落が起こりやすい時期です。
よく見られる事故は、以下のとおりです。
- ベッドからの転落
- ストレッチャーからの転落
- 抱っこ紐からの転落
- 伝い歩きや一人歩きの際の転倒
- 保護者を後追いして転倒・転落
高い位置からの転落では、頭部外傷によって命の危険につながることもあることを覚えておきましょう。
乳児期の転倒・転落を予防するには、患児一人ひとりを正しくアセスメントすることが重要です。身体機能の一般的な流れについて把握し、アセスメントに役立てましょう。
| 生後3~4ヵ月 | 定頸(首がすわる) |
| 生後5~6か月 | 寝返り |
| 生後8~9か月 | お座り |
| 生後9~10か月 | ハイハイ |
これらはあくまでも目安です。
小児の成長・発達の程度は個人差が大きく、それもまた事故につながりやすい一つの原因であるといえます。

乳児後期は「昨日できなかったことが今日できるようになった」ということも少なくありません。本人も家族も「できるようになった」と認識しますが、まだ不安定であり、予期せぬタイミングで転倒や転落が起こることもあります。
幼児の転倒・転落の特徴
幼児期は、身体発育のスピードが乳児期よりゆるやかになります。しかし、歩行や階段の昇降が可能になるため、転倒・転落のリスクは高く、保護者や看護師が十分に安全危機管理をおこなう必要があります。
幼児期によくみられる転倒・転落は以下のとおりです。
- 走っている際に転倒
- ジャンプの着地に失敗し転倒
- 階段昇降中に足を踏み外し転倒・転落
保護者や看護師には、幼児期に起こりやすい転倒や転落について理解し、適切な予防行動が求められます。
学童の転倒・転落の特徴
学童期になると転倒・転落のリスクは低下しますが、入院中は特殊な環境やデバイス類の装着などによって転倒の可能性が高いといえます。
- 点滴やモニターなどを装着した状態でトイレへ行って転倒
- 車椅子の使用中に転倒・転落
- ギプスや松葉杖使用中の転倒
この時期の小児は、コミュニケーション能力や危険察知能力が身についてくるため、転倒や転落の危険性と予防方法について本人にわかりやすく指導することが重要なポイントです。
小児の転倒・転落予防の看護計画
ここでは、転倒・転落予防の看護計画について、発達段階別にご紹介します。看護のポイントについても解説しているため、参考になりましたら幸いです。
看護問題は「転倒・転落リスク状態」、看護目標は「入院中に転倒・転落を起こさない」とします。
乳児期
OP
- 身体機能の獲得状況(寝返り、定頸、お座り、ずりばい、ハイハイなど)
- 保護者の付き添いの状況
- ベッド柵が最上段まで上がっているか
- ベッド上におもちゃや衣服などが広がっていないか
- 人見知りや後追いの状況
TP
- 患児の身長や動きに合ったベッドを選択する
- ベッドの脚部のストッパーがかかっていることを確認する
- ベッド柵は必ず最上段まで上げ、固定を確認する
- 環境整備をおこない、ベッド上に物を置かない
- 点滴やモニターのコード類を整理する
- 保護者が不在になる場合は病室で見守る。つきっきりが難しい場合は、ベッド柵が上がっていることを確認したうえで、病室のカーテンを開け、スタッフからすぐに見えるように整える
ベッド上のおもちゃや絵本、衣服、おむつなどを踏み台にして、ベッド柵の上から転落することがあります。
EP
- 家族に付き添い入院を依頼する
- 家族に乳児期の転倒・転落のリスクと防止策について説明し理解してもらう

転倒・転落防止には、保護者の協力が必要不可欠です。自宅とは異なる環境であるため、病床で起こりやすい事故について十分に説明しましょう。
幼児期
OP
- 身体機能の発達状況(つたい歩き、歩行、走る、ジャンプなど)
- コミュニケーション能力の状況(話を理解できるか、言葉で伝えられるか)
- 家族の付き添い状況
- ベッド柵が最上段まで上がっているか
- ベッド上に物が散乱していないか
- 履物の種類
- 車椅子や松葉杖の使用状況
TP
- 患児の動きや身長に合わせたベッドを選択する
- ベッド柵は最上段まで上げ、固定を確認する
- ベッドのストッパーをかける
- 車椅子やストレッチャーへの移乗時や、病院内の移動時に付き添う
- 保護者が不在になる場合は病室で見守る。つきっきりが難しい場合は、ベッド柵が上がっていることを確認したうえで、病室のカーテンを開け、スタッフからすぐに見えるように整える
EP
- 転倒や転落の危険性と防止策について、発達に合わせてわかりやすい言葉で説明する。家族にも説明する
- 移乗や移動の際はナースコールで知らせるよう伝える
- ベッド上を整理整頓するよう指導する
- 歩行時はかかとのある靴を履き、スリッパやサンダルを使用しないよう指導する
「走ると転んじゃうよ。手をつないでゆっくり歩こうね。」
「歩く時は、必ずお母さんやお父さん、看護師さんと一緒に歩こうね。」
学童期
OP
- 性格、突発的な行動の有無
- 履物の種類
- 理解力
- 安静度や活動制限
- 点滴やモニター類の種類
- 車椅子や松葉杖の使用状況
- 家族の付き添い状況
TP
- 移乗時や移動時に付き添い、不安定になった際にはすぐ手を差し伸べる
- 環境整備をおこない、ルート類が絡まらないようにする
- 家族の付き添いがない際は、ナースコールを患児の手元に置き、よく使うものは手に届く位置に置いておく
EP
- 転倒や転落の危険性について説明し、理解を得る
- 移乗時や移動時は必ず看護師を呼ぶよう指導する
- かかとのある履物を履くよう指導する
- ベッド柵をつけるよう指導する

学童期は「低床ベッド」を使用することが多いです。ベッド柵は手ではめ込むタイプのものが多いので、患児の理解力に合わせて使用しましょう。日中は足側のみ外してもよいですが、就寝時には必ずすべての柵をつけましょう。
小児の転倒・転落発生時の対応
いくら適切な予防策を講じていても、予期せぬ場面やタイミングで転倒や転落が起きてしまうことがあります。
転倒・転落発生時の基本的な対応は以下のとおりです。
- 反応・意識レベルの確認
- 外傷部位、疼痛、出血の有無と程度について確認
- バイタルサイン測定
- 医師・リーダー看護師・受け持ち看護師へ報告
- 記録

1.の段階で「反応がない・乏しい」「意識レベル低下」状態であれば、その場を離れず大きな声あるいはナースコールで応援を要請しよう。嘔吐がある場合は側臥位とし、誤嚥を予防します。
転倒・転落による疼痛や、頭部外傷による症状は、遅れて出現することがあります。転倒・転落時に問題がなかった場合でも、慎重に経過を観察する必要があります。異常時はすぐに医師へ報告しましょう。
まとめ
今回の記事では、小児の転倒・転落の特徴や看護計画について解説しました。小児の転倒・転落を予防するには、患児の身体能力やコミュニケーション能力などについてアセスメントをおこない、個別性を踏まえた計画を立案することが大切です。
患児や家族と関わる際は、常に安全管理の視点をもつことを心がけましょう。


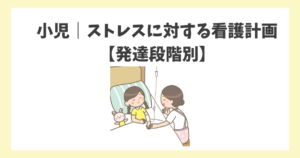
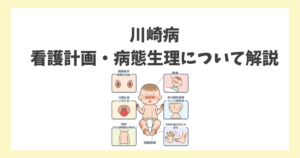
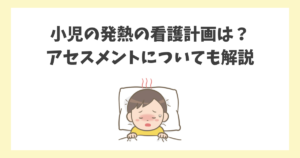
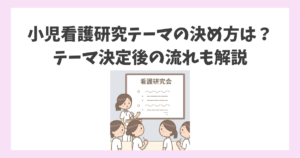
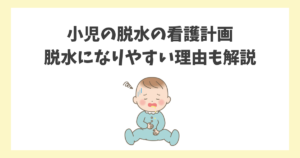

コメント