「小児看護のゼミに入っているけど研究テーマがわからない」「どんな研究にすれば評価されるのかわからない」このような悩みをもっている看護学生の方や、小児科看護師の方も多いでしょう。
看護研究のテーマ決めは、研究の出来を大きく左右する重要なポイントです。テーマが定まらなかったり、研究の途中で行き詰ったりする可能性があります。
この記事では、小児看護の研究テーマを一覧でご紹介します。テーマの選び方のポイントや、テーマを決めた後の流れについても解説します。
小児分野で看護研究に取り組む方の参考になりましたら幸いです。
小児看護研究のテーマの選び方
小児看護研究のテーマの選び方のポイントは、以下の3つです。
- 研究の目的を明確にする
- 興味があるテーマを選ぶ
- 先行研究を参考にする
ひとつずつみていきましょう。
研究の目的を明確にする
まず、研究の目的を明確にする必要があります。ここが定まっていないと研究が成立しなかったり、途中で軸がブレたりすることがあります。
興味があるテーマを選ぶ
自分が興味のあるテーマを選ぶのも、重要なポイントです。選んだテーマがどれほど「評価されそう」なテーマであっても、自分自身が興味をもてない場合は研究に対するモチベーションが保てないでしょう。テーマを決める際は、まずは自分が興味を持っていることをピックアップしましょう。

どんな小さなことでも大丈夫!まずは興味のあることをピックアップしてみましょう。
学生さんの場合は小児看護学実習、看護師さんの場合は日々の臨床業務のなかで抱いた疑問や、自分自身への課題などがあれば、メモしておくと研究のヒントを得やすくなります。
先行研究を参考にする
看護研究の目的は、
先行研究を分析し、同じテーマであっても「新しい視点」からのアプローチを探すのがポイントです。
小児看護研究のテーマ覧
小児看護研究のテーマの一覧を、以下の5つの分野に分けてご紹介します。
- 小児の成長・発達
- 小児疾患と看護
- 小児のメンタルヘルス
- 小児の家族支援
- 小児の医療環境と看護
ひとつずつみていきましょう。
小児の成長・発達
小児看護の大きなポイントでもある、成長・発達に合わせた関わり。看護研究においてもテーマに取り上げやすいといえます。ただし、漠然としたテーマにしてしまうと、何を明らかにしたいかがわからない研究になってしまいます。
「どの発達段階の」「どんなことに」絞った研究をするのか、よく考える必要がありそうです。
発達段階ごとのテーマ例は、以下のとおりです。
| 発達段階 | 研究テーマ |
|---|---|
| 新生児期 | NICUにおけるカンガルーケアが父子関係に与える影響「父親」に焦点を当てる |
| 乳児期 | 乳児の夜泣きと保護者のストレス管理 夜泣きの要因と看護師が提供できるケア |
| 幼児期 | 幼児期における偏食が食習慣形成に及ぼす影響 幼児の偏食の原因・克服方法と保護者へのアプローチ |
| 学童期 | スクリーンタイムが学童期の睡眠に及ぼす影響 デジタルデバイスの生活への影響を調査・考察 |
| 思春期 | SNS使用が思春期のメンタルヘルスに及ぼす影響 「誤ったSNSの使い方をする」ことによるメンタルヘルスへの影響 |
マーカーで示した部分が「面白い切り口」になるのではないでしょうか。

あくまでも一例です。同じ研究がすでにされていることもあるため、ご自身でよくリサーチしてください。
小児疾患と看護
疾患と看護については「疾患名」と「ターゲット」を明確にすることが重要です。

同じ疾患を扱うのでも、研究のターゲットが「患児」なのか「家族」なのかによってアプローチが異なります。
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 小児のインフルエンザへの看護介入 | 発熱や呼吸障害がある患児への酸素療法や輸液管理の有効性を検討 |
| 小児ぜんそくの管理と患児への指導 | 長期管理薬の使用法や環境要因の改善指導が発作予防に与える影響を研究し、家族ではなく患児への指導方法を検討 |
| 小児糖尿病の自己管理支援 | 血糖測定・インスリン注射の習慣化支援と、保護者のサポートが患児の自立度に与える影響を検討 |
| 先天性心疾患の子どもへの看護アプローチ | 術前・術後のケアと、成長に伴う心機能管理の重要性を分析 |
| 小児がん患者の心理的サポートと家族支援 | 長期入院中の患児が感じる不安や孤独感を軽減するための具体的な支援方法を検討 |
小児のメンタルヘルス
小児の心理的な問題に対する看護支援について、どのような介入が効果的かを考えるテーマです。近年、子どものメンタルヘルスへの関心が高まっており、看護師の心理的なケア能力がより求められています。
| テーマ | 内容 |
| 小児のストレスとそのケア方法 | 入院や検査を受ける子どもに対する心理的支援の手法と効果を検討。 |
| いじめを受けた子どもの心理的ケア | いじめによるPTSDの症状と、スクールカウンセラー・看護師による介入効果を研究。 |
| ADHDの子どもへの看護支援 | ADHD児の生活リズム改善プログラムや、看護師による行動支援の実践例を分析。 |
| 不登校児に対する看護の役割 | 不登校児が抱える心理的要因に対する看護師の介入効果と家庭支援の必要性を検討。 |
| 小児の入院ストレスを軽減する看護介入 | 入院患児へのプレパレーションの実施方法と、ストレス軽減に与える影響を研究。 |
小児の家族支援
| テーマ | 内容 |
| 小児の在宅医療と家族の負担軽減 | 医療的ケア児を持つ家族のストレス管理と、レスパイトケアの活用方法を分析。 |
| NICU退院後の親のメンタルサポート | NICU退院後の母親の心理状態と、退院指導の充実が育児ストレス軽減に与える影響を研究。 |
| 小児がん患者のきょうだい支援 | 兄弟姉妹の心理的負担の実態と、適切な支援策を模索。 |
| 障がい児を持つ家族の看護師の役割 | 親の介護負担を軽減する看護介入の実践例を分析。 |
| 小児の終末期ケアにおける家族の関わり | 家族のグリーフケア支援と、看護師が果たす役割を探る。 |
小児の医療環境と看護
| テーマ | 内容 |
| 小児病棟の環境が子どもに与える影響 | 病室のデザインや設備が入院中の子どもの心理状態に及ぼす影響を研究。 |
| 病院でのプレパレーションの効果 | 手術や処置前に適切な情報を提供することで、不安を軽減する方法を検討。 |
| 小児患者に対する看護師のコミュニケーション技術 | 年齢別の効果的な説明方法と、親子関係への影響を分析。 |
| 医療的ケア児に対する地域看護の取り組み | 訪問看護と地域連携による支援の重要性と実施状況を調査。 |
| 小児看護におけるICTの活用(遠隔診療など) | 遠隔診療・オンライン相談が親の育児不安軽減に与える影響を研究。 |
小児看護研究のテーマを決めた後の流れ
研究テーマを決めたあとは、先行研究を分析し、研究計画書を作成します。
先行研究の分析
研究テーマが決まったら、まずは先行研究を分析しましょう。関連論文を探し、既存の研究で「すでにわかっていること」と「残されている課題」を整理し、今回の研究によって新たな視点を提供できるかを考えます。
先行研究の分析には、看護学の論文が掲載されているデータベースを活用しましょう。
国内では以下の2つが有名です。
- CiNii Articles(サイニー)
- 医中誌Web
英語が読める方は「PubMed」「Google Scholar」など、海外のサイトも見てみると情報量が増えます。これらのサイトで、自分の研究テーマに関連する論文を検索し、内容を比較しながら不足している視点を見つけましょう。
研究計画の立案
先行研究の分析が終わったら、研究計画を立案します。研究計画とは、研究を進めるための具体的な指針を示すものです。研究の目的を明確にし、途中で軸がブレないようにするために重要です。
研究計画書には以下の内容を記載しましょう。
| 項目 | 記載する内容 |
|---|---|
| 研究タイトル | 研究のテーマを簡潔に |
| 研究の背景と目的 | 研究をおこなう理由と、先行研究tの関連性 |
| 研究の意義 | 研究が看護にどのように貢献するか |
| 研究方法 | 質的研究・量的研究どちらにするのか 調査や実験などの具体的な方法 |
| 対象者 | 研究の対象となる集団 |
| データ収集方法 | アンケート、インタビュー、観察など |
| データ分析方法 | 収集したデータをどのように分析するのか |
| 倫理的配慮 | 個人情報保護、インフォームドコンセント、倫理委員会の承認など |
| スケジュール | 今後の進行について |
| 仮説・期待される結果 | 研究からどのような知見を得られるのか |
| 参考文献 | 関連する先行研究の論文など |
質的研究と量的研究の違いは以下のとおりです。
| 量的研究 | 質的研究 | |
|---|---|---|
| 目的 | 数値データによって客観的に分析する | 主観的な経験や意味を深く理解する |
| データの種類 | 数値(統計データ) | 言葉、記述など |
| データ収集方法 | アンケート(数値)、実験、観察 | インタビュー、アンケート(記述)、ケーススタディーなど |
| 分析方法 | 統計分析 | テーマ分析、コード化など |
| サンプルサイズ | 大規模(多くの対象者) | 小規模(少人数) |
| 結果の一般化 | しやすい | 個別の事例を深く考察 |
| 向いているテーマ | 数値測定が可能 因果関係の検証 統計的な分析が可能 | 行動や感情の背景を探る 患者や看護師の視点から考える 社会的・文化的な要因を考慮 |

例えば、同じ「NICUにおけるカンガルーケアが父子関係に与える影響」というテーマであっても、カンガルーケア中の父親のバイタルの変動をみる場合は「量的研究」、父親にインタビューして思いを話してもらう場合は「質的研究」ということになります。
研究計画の作成においては、量的研究と質的研究のどちらの方法を用いるのかを明確にし、それに適した研究デザインを構築することが求められます。
研究の流れをしっかりと計画し、意義のある研究にしていきましょう。
小児看護研究テーマを決める際の6つの注意点
小児看護の研究テーマを選定する際には、6つのポイントを意識する必要があります。
- 臨床現場のニーズを考慮する
- 実現可能性を検討する
- 先行研究を十分に調査する
- 量的研究と質的研究の選択を慎重におこなう
- 倫理的配慮について考える
- 研究結果の活用を意識する
順に解説します。
臨床現場のニーズを考慮する
小児看護の現場で課題となっているテーマを選ぶことで、実用性の高い研究が可能になります。可能な範囲で医療スタッフや保護者の声を参考にし、現場の課題を反映したテーマを選定すると、より実りのある研究となるでしょう。
実現可能性を確認する
研究を進めるためのリソース(時間、データ収集の手段、協力者の確保)が十分にあるかを確認しておく必要があります。倫理的配慮やデータ収集の難易度を考慮することも大切です。難易度が高いと、研究期間内に終えられなかったり、途中で研究の継続が難しくなったりする可能性があります。
先行研究を十分に調査する
既に同じテーマで多くの研究が行われている場合、新たな視点を加える工夫が必要です。類似研究の傾向を把握しましょう。
倫理的配慮を忘れない
研究対象となる小児や家族の個人情報保護、インフォームド・コンセントの取得など、倫理的配慮を忘れないようにしましょう。研究内容によっては、倫理審査が必要となることもあります。
研究結果の活用を意識する
研究は、今後の臨床に活用するためのものです。研究の成果が、実際の看護ケアの向上や政策提言に役立つかを事前に考慮することが重要です。
研究発表や論文執筆を通じて、より多くの医療関係者に成果を共有できるよう準備しましょう。

「研究が終わったから終わり♪」とするのではなく、今後の看護に活かす方法を考えましょう。研究は、看護の質を向上させるためのものであることを忘れずに。
まとめ
今回は、小児看護研究テーマの選び方や具体例、テーマ決定後の流れについて解説しました。重要なポイントを整理します。
- 研究テーマは自分が興味のある分野を選ぶ
- 関連する先行研究の分析を十分におこなう
- 実現可能なテーマかを熟慮する
- 研究結果を今後の看護にどう活用するかを考える
看護研究を成功させるには、研究計画を充実させておくことが重要です。今回ご紹介した内容をもとに、ぜひ「楽しい」研究テーマを選んでみてください。


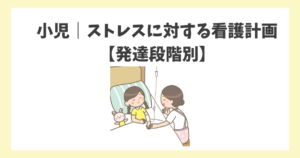
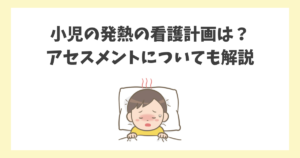

コメント