「小児実習大変だった。でもこの後またレポートを書かないといけない…」
「書いてはみたけど内容が浅い気がする…」
小児看護学実習まとめレポートの書き方に悩んでいる看護学生さんは少なくないでしょう。
この記事では、そんな看護学生さんへ向けて、小児看護学実習後に提出する「学び・振り返りレポート」の書き方のコツをわかりやすく解説します。
小児科で実習指導をしていた際に多くの学生にアドバイスしてきた内容を、そのまま記事にまとめました。
最後には、レポートの見本の販売ページもご案内しています。ぜひご覧ください。
看護学生さんの負担を少しでも減らすお手伝いができたら幸いです。
レポートを書く前に!実習の「目的」や「目標」を確認しよう
小児看護学実習まとめレポートを書く前に、まず実習の目的や目標を再確認しましょう。
なぜなら、小児看護学実習の学びレポートでは、以下の2点をアピールする必要があるからです。
- 小児看護学実習の目的を果たせた
- 小児看護学実習の目標の一部もしくは全部を達成できた
それぞれ解説します。
目的
小児看護学実習の目的は、学校によって多少異なるものの、だいたい以下のような内容だと思います。
小児の心身の成長発達を理解し、それに応じた看護の実践能力を身につける。さまざまな健康状態にある子どもとその家族に、適切な看護を実践する能力を養う。
レポートを書く際は、この目的を意識して書く必要があるのです。
以下の3点を意識してみましょう。
- 小児の発達段階を意識した関わりができたエピソード
- 病気や入院によって不安を感じる子どもに、どう寄り添ったか
- 家族への配慮や支援を意識できた場面
これらの体験を通して、「子どもの成長発達への理解」や「家族を含めた包括的な看護の実践」にどうつながったかを、自分の言葉で振り返りまとめることがポイントです。
目標
以下は、多くの看護学校で共通している代表的な目標の例です。
小児をひとりの人として尊重し、権利を持つ存在と理解する
健康障害や入院が与える影響を考え、発達段階をふまえた支援を実践する
遊びや生活支援など、子どもに合った日常生活援助ができる
小児の成長を支える家族への支援について考え実践する
小児を取り巻く医療・保健・福祉・教育の連携と、看護の役割を理解する
レポートでは、実習において上記の目標に沿って行動できたことを示す必要があります。
以下のようなシチュエーションとそこから得た学びについて書くと効果的です。
- 子どもの気持ちや意志を尊重できた場面
- 病気や入院による不安や混乱に気づき、寄り添えたエピソード
- 発達に合った日常生活支援・遊びの工夫の具体的な内容
- 家族に対する支援や配慮
- 多職種や連携の重要性を感じた場面
目標に沿ってレポートを書くと、学びが具体的に伝わりやすく、教員からの評価も上がりやすいのではないでしょうか。
小児看護学実習レポート|基本の構成5ステップ
小児看護学実習の学びレポートにおける基本の構成は、次の5つのステップからなります。
- 自分自身が掲げた実習目標と意気込み
- 受け持った・関わった患児の情報
- 実習中のエピソードと学び(2~3エピソード)
- 今後に活かしたいことと残された課題
- まとめ・総括
それぞれ解説します。
自分自身が掲げた実習目標と意気込み
まずは、自分がどんな目標を持って実習に臨んだかを振り返り、レポートの読み手に伝わるようにしましょう。
例)小児の成長発達に応じた声かけや関わりを学び、子どもと信頼関係を築ける看護師を目指したいと思った
このパートでは、自分の想いを「具体的に」「前向きに」書くことが大切です。
受け持った・関わった患児の情報
受け持ったあるいは関わった患児の情報を簡潔にまとめます。
- 年齢と発達段階(例:5歳/幼児期)
- 診断名(例:喘息)と入院理由
- 主な症状
- 家族構成や背景(例:母子家庭、祖母付き添いなど)
患児の概要すべてを書く必要はありません。
今回のレポートで触れるエピソードに関わる項目について、簡潔にまとめましょう。
実習中のエピソードと学び
ここがレポートの核となるパートです。実際のエピソードを2~3個程度あげ、そこから得た学びを書きましょう。
 ナースもも
ナースももエピソードが少なすぎたり、多すぎたりするのはNG。レポートとしてまとめづらくなります。
各エピソードは「背景 → 関わり → 学び」の順で書くと、読み手に伝わりやすくなります。学びは実習目標とリンクさせて、「どう成長につながったのか」を明確にしましょう。
また、体験を振り返る際には、自分の感情や迷いも素直に書くとリアリティが出ます。
ここでは、具体例を3つほどご紹介します。
エピソード①:遊びを通じた信頼関係の構築
※実習目標「遊びや生活支援などを通して子どもに合った日常生活援助ができる」に沿って記載した例
【エピソード】
実習初日は検温を嫌がっていた3歳の患児に対し、看護師がぬいぐるみを使って「お医者さんごっこ」をしたことで、笑顔で検温に応じるようになった。
この関わりを見て、自分も同じようにぬいぐるみや絵本を活用して関わったところ、患児の表情がやわらぎ、少しずつ距離が縮まった。実習開始後数日経つと、学生の検温にも応じてくれるようになった。
【学び】
遊びは単なる「楽しい時間」ではなく、信頼関係を築くための大切な看護技術であると実感した。子どもに合った表現方法を取り入れることで、より安心感のあるケアが可能になることがわかった。
エピソード②:病気による心理的な影響に気づいた場面
※実習目標「健康障害や入院が与える影響を考え、発達段階をふまえた支援を考える」に沿って記載した例
【エピソード】
家庭の事情によって夜間の付き添いがない患児が「ママがいい」と泣いて不安を訴え、入眠できなかった。少しでも不安が軽減されるよう、学生として入眠前用の絵本を作成し、看護師に読んでもらった。その結果、患児は絵本を気に入り、毎日のイブニングケアを楽しみにし、少しずつ泣かずに眠れるようになった。朝母の姿を見ると「一人で寝られたよ」と得意そうに話していた。
【学び】
家族と離れることへの不安の大きさを実感した体験となった。また、患児が普段から好きな「絵本」というツールを用いて、不安に寄り添う看護が実践できた。病気だけでなく、子どもの心への影響にも配慮する看護が重要だと学んだ。
エピソード③:家族への配慮を意識した関わり
※実習目標「小児の成長を支える家族への支援について考える」に沿って記載した例
【エピソード】
母子家庭であり、日中は祖母が可能な範囲で付き添っていた患児。母親が「仕事で来られず、病状や本人の精神面が心配」と話していたが、日々の受け持ち看護師が患児の生活の様子やバイタルサインの推移をメモに記載し、母が来た際に渡していた。また、「何か気になることやわからないことがあればいつでもおっしゃってくださいね」と声かけをしていた。母は「本当にありがとうございます。安心できます。」と話していた。
【学び】
家族の不安や葛藤を理解し、子どもだけでなく家族も看護の対象であることに気づけた。情報共有や一言の声かけが、家族への安心感につながることを実感した。
今後に活かしたいこと・残された課題
「今後に活かしたいこと」と「残された課題」は、自分の成長意欲をアピールできる大事なパートです。
「学んで終わり」ではなく、「次にどうつなげるか」を明確に言語化できると、教員からの評価もきっと高くなるでしょう。
「できなかったこと」「迷ったこと」「自信が持てなかった場面」も取り上げ、今後の課題として整理することが大切です。
今後に活かしたいこと
今後に活かしたいことについてまとめる際は、実習中の成功体験をベースにすると書きやすいです。「どんな関わりができて、子どもや家族にどんな反応があったか」を振り返ってみましょう。
また、「これからも続けたい」という前向きな気持ちを書くことで、看護観や信念につながる内容にすると、説得力のあるレポートになるでしょう。
実習中に〇〇という関わりを行い、〇〇という反応があった。
この経験から、今後は〜〜な場面でも〇〇できるような看護師を目指したい。
【例文】
小児は自分の感情をうまく表現できないことが多いが、不安や緊張を受け止める姿勢を忘れず、「安心できる存在」になれるような看護を目指したい。
残された課題
「できなかったこと」だけでなく「気づけたこと」もセットにして、前向きなトーンにすることが大切です。単なる反省ではなく、気づきを成長のきっかけに変える視点をアピールしましょう。
このパートでは、感情や迷いを素直に表現しても大丈夫です。実習中の戸惑いや不安を振り返ることで、リアルな自己評価になります。
そして、今後どう改善したいかまで示しましょう。「もっと○○できるようにしたい」「〜を意識して関わっていきたい」などと、次へのアクションを添えてみてください。
実習中に〇〇という場面で、〇〇がうまくできなかった。
今後は〜〜を意識し、〇〇できるように取り組みたい。
【例文】
家族との関係構築に時間がかかり、十分な声かけや関わりができなかった。今後は「看護師の一員として」自信を持って関わっていけるようにしたい。
まとめ・総括
まとめのパートでは、以下の3点を意識しましょう。
- 実習前と比べた「自分の変化」を書く
- 小児看護ならではの学びを盛り込む
- 今後にどうつなげるか、将来像を描く
実習全体を通しての気づきや自分の成長について書くのがポイントです。
【例文】
子ども一人のケアだけでは不十分であり、家族との連携・多職種との協力も含めて“チームで支える”看護の重要性を学んだ。



「とても勉強になった」「貴重な経験だった」だけで終わってしまうのは、よくあるNGパターンです。学びをただ並べるだけで、自分の変化や想いが書かれていないのも×。
レポートを書くときのコツ3つ
小児看護学実習レポートを書く際に意識したい基本のコツを3つご紹介します。
- 自分の言葉で書く
- 目的や目標とのリンクを意識する
- 結論→理由・背景の流れで書く
このポイントを押さえることで、説得力があり、評価されやすい内容に仕上がります。
自分の言葉で書く
一番大切なのは、「自分の言葉で書く」ということです。
ネットの例文や参考書の内容をそのまま写すのではなく、あくまで自分自身が経験して感じたこと・学んだことを、自分の言葉で表現することを意識しましょう。
「なんとなくこう感じた」でも大丈夫。
その気持ちに具体的な出来事を添えていけば、自然と深みのある内容になります。
また、この記事の最後にご紹介しているレポートのサンプルは、自由にアレンジできるようになっています。
目的・目標とのリンクを意識する
レポートでは、「この体験が実習の目標とどうつながるのか?」「どの目標が達成できたのか?」という視点がとても重要です。
ただ出来事を並べるのではなく、それが実習目標のどれに該当するかを考えることで、内容に意味が生まれます。
書いたエピソードを実習目標に照らして言語化しましょう。
結論 → 理由・背景の流れで書く
「〇〇だと感じた」「〜に気づいた」という結論だけを書いてしまうと、レポートとしては少し物足りない印象になってしまいます。
大事なのは、「なぜそう思ったのか」という理由や背景、体験エピソードをセットで書くことです。
【NG例】
「子どもは安心できる関わりを求めていると感じた。」
【伝わりやすい例】
「初日は検温を嫌がっていたが、ぬいぐるみを使って遊びながら促したところ、自分から体温計を手に取り協力してくれた。その姿から、子どもは安心できる関わりを求めていると感じた。」
まとめ
小児看護学実習レポートでは、出来事を並べるだけでなく、「自分がどう関わり、何を感じ、どう成長したか」を言葉にすることが大切です。
実習の目的や目標とつながるエピソードを盛り込み、自分の言葉で丁寧に振り返ることで、看護師としての視点や成長がより明確になります。
あなたの実習レポートが、自信につながる一歩になりますように。応援しています。
忙しい方のために:そのまま使えるレポートテンプレートもあります
たった数分で完成!小児実習レポート、もう悩まなくていい!
小児実習、頑張ったあなたへ
「レポート…正直もうムリ…」
「書く時間も気力もない」
そんな看護学生さんの声から生まれた、そのまま使える小児看護実習レポートテンプレートを2種類ご用意しました。
こんな方におすすめです
- 実習後でヘトヘト、レポートにまで手が回らない
- とにかく“形”にして提出したい!
- 書き方がわからなくて一文字目から手が止まっている
テンプレートには、以下の3種類あります。
- 川崎病の乳児の例
- 気管支喘息の幼児の例
- ネフローゼ症候群の学童の例
アレンジがきくので、疾患や年齢が異なっても大丈夫。
3種類を見比べて、書きやすそうなものを選んでください。
提出までの時間がない、でも手抜きにはしたくないあなたへ。
「実習の頑張りを、レポートでもちゃんと形にする」その手助けになることをお約束します。
ぜひチェックしてみてください。

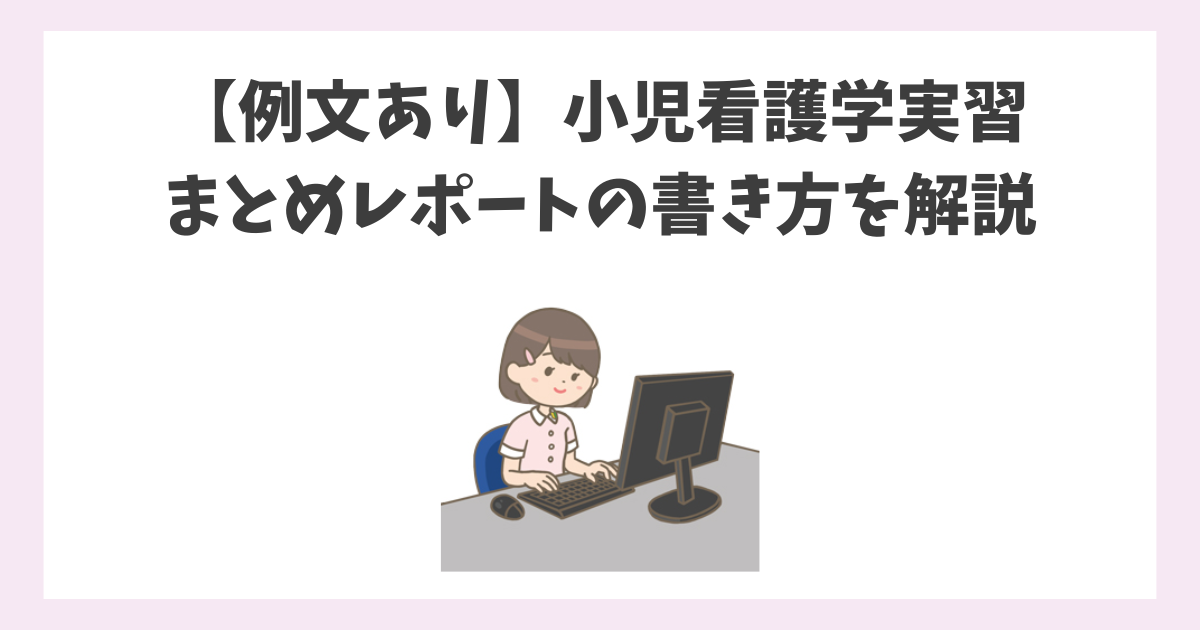
コメント