小児看護は、子どもとその家族を対象とし、成長と回復をサポートする専門的な看護分野です。子どもが好きで、小児科で働いてみたいと考える方も多く、人気のある診療科です。
一方で、実際にどうやって小児科看護師になるのか、どんな人が向いているのか不安に感じることもあるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、小児科看護師を目指す方法から、向いている人の特徴、働く魅力、そしてその先のキャリアアップまで、小児科看護師歴10年の私が、体験談を交えながらわかりやすく解説します。
「どうやったら小児科看護師になれる?」「向いていないかもしれない…」このような悩みを抱えている方の参考になりましたら幸いです。
小児科看護師になる方法

小児科看護師になるのに、看護師免許以外に特別な資格は必要ありません。
基本的なルートは他の診療科と同じです。
ここでは、小児科看護師になるための基本的な流れと、未経験でも目指せる方法について具体的に見ていきましょう。
まずは看護師免許の取得が必要
小児科で働きたい場合、他の診療科と同じように、まずは看護師としての国家資格の取得が必須です。
看護師資格を取得するには、看護師養成校(看護専門学校・短期大学・看護系大学など)で所定のカリキュラムを修了し、看護師国家試験に合格する必要があります。
看護師免許を取得すれば、どの診療科に進むかは自分の希望次第。その中で小児科を選び、経験を積んでいくことで、小児看護師としての道が開けていきます。
学生時代に余裕があれば、国家試験勉強の際に小児分野にとくに力を入れる、専門書を読むことで小児看護への理解を深めるなどの準備をしておくと、小児看護師になってから大いに活用できるでしょう。
小児科看護師は未経験でも目指せる
小児科看護師は、未経験でも目指せます。
新卒の場合は、就職先を探すうえで小児科があるかどうかを確認しましょう。診療科の希望を出せる職場とそうでない職場があるため、希望が出せるかどうかも確認しておくと安心です。
また、日本には30以上の「こども専門病院」や「小児医療センター」などがあります。これらはすべての患者さんが「子ども」であるため、どの部署に配属したとしても小児看護に携わることが可能です。
小児科クリニックで働く選択肢もありますが、新卒の段階では大きな病院や病棟で経験を積んだ方が、基本的な技術や知識が身につきやすいといえます。クリニックによっては新卒を採用していないこともあります。
新卒ではない場合は、小児科への転向理由と目的を明確にしておきましょう。
一般的な技術や知識が習得できていれば、就職先の幅が広がります。小児科クリニック、重症児デイサービス、保育園なども視野に入れて考えられるでしょう。
小児科看護師に向いている人の特徴5つ
小児科で働くうえでは、人柄や子どもとの向き合い方が何よりも大切です。
ここでは、小児科看護師に向いている人の特徴を5つご紹介します。
子どもが好きな人
小児科で働くうえで、子どもが好きという気持ちはとても大切です。
単に「かわいい」と思うだけではなく、辛い思いをして泣いていたり不機嫌だったりしても、その子に寄り添いたいと思う気持ちこそが、信頼関係の構築につながるのです。
自分の症状や思いをうまく言葉にできない子どもたちにとって、安心できる大人の存在はとても大きなもの。
「子どもが好き」という気持ちがあれば、日々の関わりの中で、「あなたがいてくれてよかった」と思ってもらえるやりがいを感じられるでしょう。
観察力がある人
小児科では、子ども自身が不調をうまく伝えられないことも多く、ちょっとした変化に気づける観察力がとても大切になります。
「いつもより元気がないな」「泣き方が違うかも?」などといった小さなサインに気づくことが、早めの対応やケアにつながります。
注意深く子どもを見守ることが、安心・安全な看護に直結するのです。
繊細で丁寧なケアができる人
子どもは、心身共に大変繊細であるため、小児科看護師にはひとつひとつの処置や関わりを、やさしく丁寧に行える人が向いています。
たとえば注射のときに不安でいっぱいな子どもに対して、痛みだけでなく気持ちにも配慮できる関わりがあると、子どもの安心につながります。
また、何気ない一言や笑顔が、緊張していた子の気持ちを和らげてくれることも。
一人ひとりに合わせた丁寧な対応ができる人は、子どもにとってかけがえのない存在になります。
家族への関わりを大切にできる人
小児科の看護は、子どもとご家族の両方を支える仕事です。お子さんが入院や治療を受けるとき、ご家族は、生活様式の変化やきょうだいのこと、そして何より子どもの病状のことなどについて、不安やストレスを抱えているでしょう。
そのような中で、ご家族に対して丁寧な説明や温かい言葉かけができる人は、大きな安心材料になるでしょう。「一緒にがんばりましょうね」と寄り添う姿勢が、子どもと家族の心をつなぐ看護へとつながります。
「小児科看護師向いていないかも」私自身がそう思っていました

「泣いている子どもへの接し方が分からない」「小児科の実習で自信をなくしてしまった」そんなふうに思った経験はありませんか?
実は、小児科歴10年以上の筆者も、現場で働いていて「小児科に向いていないかも」と感じていた時期もありました。
 ナースもも
ナースもも最初の頃は、注射や処置のたびに子どもたちに泣かれてしまい、落ち込むこともありました。それでも、先輩の関わり方を見て真似したり、少しずつ子どものペースに合わせて声をかけるように意識したりして毎日を必死に乗り越えていました。
次第に、泣いていた子が自分にだけは笑ってくれる瞬間があったり、「ありがと」と小さな声で言ってもらえた日には、胸がいっぱいになったのを今でも覚えています。
今では、小児科以外は考えられないくらい、この仕事が好きになりました。
向いているかどうかは、やってみて初めて分かることも多いため、「小児科看護師になりたい」という気持ちがあれば、一度その道に飛び込んでみるのもよいでしょう。
今では、最初に感じた「不安」や「戸惑い」も、乗り越えたからこそ得られるやりがいがあると実感しています。
小児科看護師として働く魅力とやりがい
ここからは、小児科看護師として働く魅力とやりがいを見ていきましょう。
子どもの笑顔や成長に寄り添える
小児科ならではのやりがいは、なんといっても子どもたちの回復や成長をそばで見守れること。
昨日まで元気がなかった子が、今日は笑ってくれたり、ちょっとした関わりの中で「ありがとう」と言ってくれたり。毎日の小さな変化の積み重ねが、何よりの喜びになります。
なかには、慢性疾患によって入退院を繰り返さなくてはならない子どもたちもいます。そのような患者さんの場合、入院のたびに成長に驚かされたり、コミュニケーションがとれるようになっていったりします。
それもまた小児科看護師のひとつの楽しみです。
家族看護を学べる
小児科では、子どもへのケアだけでなく、保護者への支援も看護の大切な一部です。
子どもが不安や体調不良を抱えているとき、そばにいるご家族もまた、不安や緊張を感じているものです。
そんなときに、わかりやすく丁寧に説明したり、気持ちに寄り添った言葉をかけたりすることで、「話を聞いてもらえてホッとしました」「安心しました」と声をかけていただけることがあります。
このような関わりを通して、子どもだけでなく家族全体を支える看護を学べるのが、小児科の大きな魅力です。
専門性を深めることでキャリアの幅が広がる
小児看護には、子どもの発達や病気に関する専門的な知識や技術が求められます。
働きながらスキルを磨いていけば、NICUや小児救急、保育園、さらには教育の場など、活躍のフィールドを広げていくことも可能です。
また、小児看護認定看護師・専門看護師などの資格取得を目指すことで、チームの中でより専門的な役割を担えるようにもなります。
小児科看護師のキャリアアップ


小児科で経験を積む中で、「もっと専門的に学びたい」「幅広い現場で活躍したい」と感じることもあるかもしれません。
実は、小児科看護師にはさまざまなキャリアアップの道があります。
ここでは、専門資格の取得や、日々のスキルアップ方法、そしてその先に広がる働き方の選択肢についてご紹介します。
小児看護に関する専門的な資格
より深い知識と技術を身につけたい方には、認定看護師や専門看護師といった専門的な資格取得をめざすのがひとつの選択肢です。
小児分野の認定看護師・専門看護師には以下の種類があります。
| 種類 | 役割 |
|---|---|
| 小児プライマリケア認定看護師 | ・救急時の子どもの病態に応じた看護 ・育児不安や虐待への対応と子どもと親の権利擁護 |
| 新生児集中ケア認定看護師 | ・ハイリスク新生児の看護 ・生理学的安定と発育促進のためのケア ・親子関係形成のための支援 |
| 小児看護専門看護師 | 子どもたちが健やかに成長・発達していけるように療養生活を支援し、他の医療スタッフと連携して水準の高い看護を提供する |
| 家族看護専門看護師 | 患者の回復を促進するために家族を支援する。患者を含む家族本来のセルフケア機能を高め、主体的に問題解決できるよう身体的、精神的、社会的に支援し、水準の高い看護を提供する |
このほかに「皮膚・排泄ケア認定看護師」「感染管理認定看護師」「感染症専門看護師」として小児領域で活躍している方もいます。
専門的な資格を取得することで、チーム内での役割が広がり、後輩の指導や家族支援の中心的存在として活躍できるようになります。やりがいにもつながるでしょう。
現場でスキルアップする方法
キャリアアップというと資格の取得を思い浮かべがちですが、日々の現場の中にも学びのチャンスはたくさんあります。以下はその例です。
- 院内で開催される小児看護の研修や勉強会
- 外部のセミナー・講演会への参加
- 子どもとの関わりや家族支援を振り返るカンファレンス など
このような場で得た気づきや学びを、日々の看護に少しずつ取り入れていくことで、自分のケアにも自信が持てるようになります。
「もっとこうしたら、この子にとって安心かも」と考えるその姿勢こそが、スキルアップへの第一歩です。
キャリアアップの先にある選択肢
小児科で経験を重ねた先には、さまざまな働き方の広がりがあります。
自分の興味や強みを活かして、より専門的な道へ進んだり、次の世代を支える立場になったりすることも可能です。
キャリアアップの例は以下のとおりです。
- PICU(小児集中治療室)やNICU(新生児集中治療室)での高度なケアに携わる
- 保育園や児童福祉施設で、子どもたちの健康を支える看護
- 教育担当やプリセプターとして、後輩の成長を支える存在に
- 看護学校や養成機関で、教える側として看護の魅力を伝える
小児看護で培った観察力・対応力・家族支援の視点は、どのような現場でも強みになります。
「子どもやご家族にもっと深く関わりたい」という気持ちが、次のキャリアの一歩につながるのではないでしょうか。
おわりに
小児科看護師は、子どもの成長や回復、そして家族を支える、やりがいのある仕事です。
小児科看護師になるまでの道のりは特別なものではなく、未経験からでも挑戦でき、日々の関わりの中で少しずつ学びを重ねられます。
向き不向きに迷うことがあっても、子どもやご家族に関わりたいという想いがあれば、それが何よりの力になります。
やりがいと成長のあるこの道で、自分らしい看護のかたちを築いていきましょう。

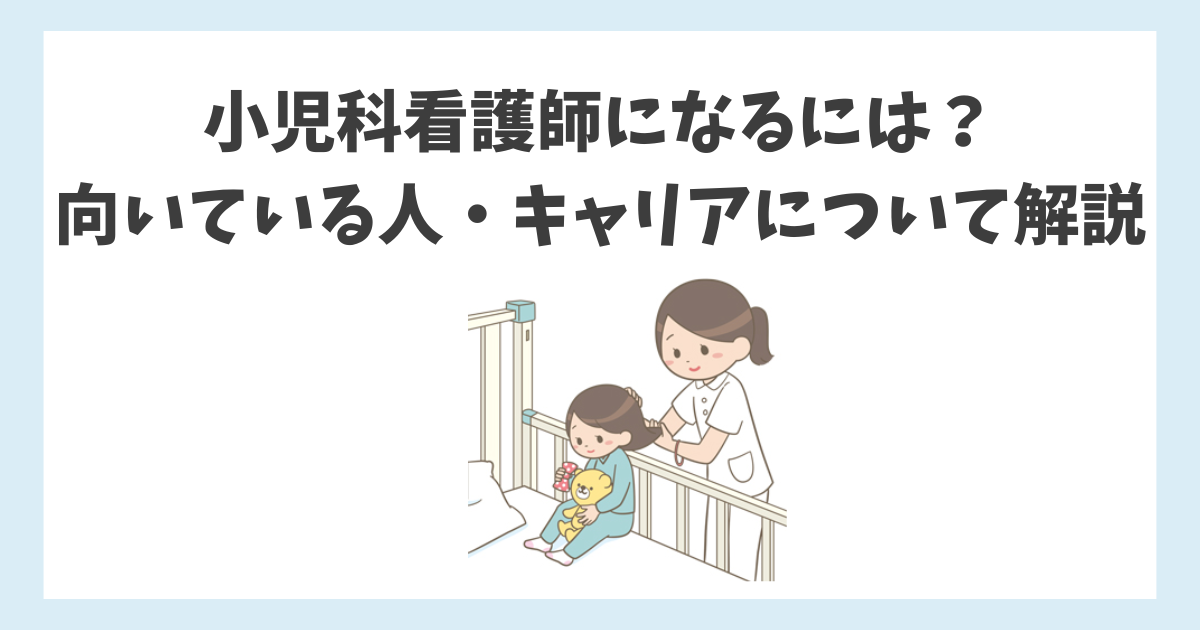
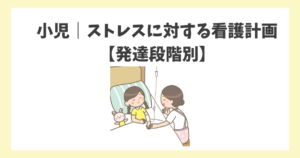
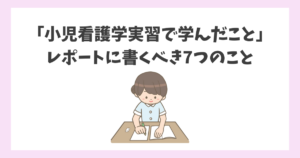
コメント