「患児が薬を嫌がりのけぞって泣いている」「やっとの思いで飲んでくれた薬をすぐに吐き出した」
小児科看護師の多くは、このような場面に遭遇した経験があるのではないでしょうか。
小児看護の現場では、服薬管理に苦労する場面が多々あります。内服を嫌がる患児や、服薬管理に不安を抱いている家族への対応は、看護師にとって大きな課題のひとつです。
この記事では、小児の服薬管理のポイントと看護計画について、発達段階別で詳しく解説します。
看護のポイントをおさえ、患児や家族にとって無理のない服薬管理をめざしましょう。
小児の服薬管理が難しい理由
小児の服薬管理を難しく感じる背景には、以下のような理由があります。
- 味覚や嗅覚が敏感である
- 内服に対する恐怖心がある
- 必要性への理解が難しい
- 保護者や看護師の必死さが伝わっている
- 保護者が服薬に対して抵抗感や罪悪感を抱いている
ひとつずつ解説します。
味覚や嗅覚が敏感である
こどもは、大人に比べて味覚や嗅覚が敏感だとされています。とくに、苦みや酸味などへの感受性が高く、薬特有の苦みや匂いを嫌がるこどもが少なくありません。
この敏感さは、0歳から6歳ころまでの乳幼児期のこどもに顕著にみられるため、この年齢の患児に薬を飲ませる際には、工夫が必要です。
こどもが苦みを感じやすい薬の例には、以下があります。
- 抗菌薬(マクロライド系):ジスロマック、クラリスドライシロップなど)
- 抗インフルエンザウイルス薬:タミフルドライシロップ
これらの薬が処方されている際は、こどもが服薬をより一層嫌がる可能性があります。
 ナースもも
ナースももマクロライド系の抗菌薬は、大人でも苦く感じます…。
内服への恐怖心がある
こどもたちにとって 「薬を飲む」という行為自体が未知の体験であることが少なくないため、恐怖心を抱いても不自然ではありません。
怖い気持ちがありながら一生懸命内服できた場合でも、その際に苦みを感じてしまうと、今回の経験がトラウマとなり、今後内服をさらに嫌がることがあります。
必要性への理解が難しい
こどもが、コミュニケーションによって話の内容や言葉の意味を正しく理解できるようになるのは、幼児後期から学童期だとされています。つまり、それより幼いこどもたちにとっては「病気を治すために薬を飲むよ」「元気になるために必要なんだよ」などと伝えても、理解が難しいのです。
保護者や看護師の必死さが伝わっている
こどもは、周囲の大人の感情を敏感に感じ取ります。保護者や看護師が必死になって薬を飲ませようとしていると、こどもはすぐにそれを察知するのです。
看護師や家族が「どうしても飲ませなければ」「飲んでくれるかな?」などといった不安や焦りを感じていると、それがこどもへダイレクトに伝わるでしょう。こどもの緊張が増強する可能性があります。
保護者が服薬に対して抵抗感や罪悪感を抱いている
患児が嫌がって泣きながら薬を飲む姿を見た保護者は「無理やり薬を飲ませるのはかわいそう」「飲ませ方が悪かったのでは」などと、こどもへの罪悪感や服薬への抵抗感を抱く方も少なくありません。
服薬がうまくできない状況が続くと、こどもだけでなく家族のストレスも緊張し、状況によっては服薬管理が難しいこともあります。
小児の服薬管理のための3つの工夫
小児の服薬管理は、こどもが薬を飲むことに抵抗を感じない環境をつくることから始まります。
- 好みの食品や飲料と一緒に摂取する
- 楽しい雰囲気づくりを大切にする
- 安心感を提供する
- 嘘をつかない・隠さない
ひとつずつみていきましょう。
好みの食品や飲料と一緒に摂取する
苦みやザラザラとした舌触りを軽減させることで、負担なく内服できる可能性があります。患児が好きなものに薬を「混ぜる」「包み込む」など工夫してみましょう。
しかし、食品によっては薬の苦みを増強させてしまうものもあるため、注意が必要です。
以下の表に、服薬におすすめの食品と、控えた方がよい食品についてまとめました。
| 薬の摂取におすすめの食品の例 | 薬と一緒に摂取しない方がよい食品の例 |
| 服薬ゼリー アイスクリーム(バニラ・チョコ) 練乳 砂糖 プリン ピーナッツクリーム ココアパウダー | 乳酸菌飲料 スポーツドリンク ヨーグルト 柑橘系のフルーツジュース |
参考:大正製薬株式会社「患者さん用クリラスロマイシンドライシロップを服用されている方へ」
酸味のある食品や飲料品を薬と一緒に摂取すると、薬の表面に施されている甘い成分のコーティングが剥がれてしまうことがあります。



私のイチオシはチョコレート味のアイスクリーム♪チョコアイスで薬をスムーズに飲めるようになった子が多かった印象です。
また、飲ませる際は以下の点にも注意してください。
- 薬が露出しないよう、食品で十分に包み込む
- 砂糖やココアパウダーを使用する際は、少量の水を加えてペースト状にする
- 使用前に必ずアレルギーの確認をする
幼児期以降の子どもでは、一緒に摂取する食品を本人に選んでもらうのも効果的です。
楽しい雰囲気づくり
小児の服薬管理においては、楽しい雰囲気づくりが大きなポイントです。
内服を「嫌なこと」ではなく「楽しいこと」と捉えてもらえるよう、声かけやアプローチに工夫を加えましょう。
具体的には、以下のアプローチがおすすめです。
- ご褒美シールやスタンプの活用
- 楽しい声かけ「元気になれるよ」「強くなれるよ」など
- 音楽や動画の活用
「薬を飲めたらシールを貼る」「頑張って飲めたら好きな動画をひとつ見られる」などのご褒美は、患児のモチベーションを向上させられるきっかけになります。ご家族と相談してみましょう。
安心感の提供
こどもが服薬に対して恐怖心を抱いている場合、その恐怖心や不安を取り除くことが重要です。看護師には、安心感を与えられるような関わりが求められます。
- 家族に抱っこしてもらった状態で内服する
- 内服の前後でスキンシップを取り入れる
- 内服の必要性を患児の年齢に合わせてわかりやすく説明する
子どもが安心感を得るためには、家族のサポートが不可欠です。抱っこや手足へのタッチングで、患児の頑張りを引き出せることがあります。
また、看護師がその場にいるだけで「怖い」と感じる患児もいるため、そのような場合には一度席を外すのも大切なアプローチのひとつです。
ただし、家族が「どうやって飲ませたらいいかわからない」「泣いて嫌がるので飲ませられない」などと困っている場合は、そばでサポートしましょう。
嘘をつかない・隠さない
「苦くないよ」という嘘や、本当は食べ物のなかに薬が入っているのに「薬じゃないよ」などといった嘘はやめましょう。子どもは気づきます。その後、医療者や保護者に対して不信感を抱きかねません。
「薬を混ぜてあるから、一緒に飲んじゃおう」「これを飲めたら、ご褒美に〇〇をもう少し食べようか」などといった声かけをおすすめします。
小児の服薬管理に関する看護計画の例


ここからは、乳児期・幼児期・学童期それぞれの発達段階について、「#非効果的健康管理」という看護診断と「服薬ができる」を看護目標と仮定した場合の、看護計画の例をご紹介します。
乳児期
- 内服は空腹時におこなう
- 水分は安全に飲み込める量にする
- 薬をミルクに混ぜることは避ける



ミルクに混ぜてしまうと、いつもの味との変化を感じ取り、ミルク拒否につながることがあります。タイミングは吸てつ反応が強くなる「空腹時」がgood!
OP
- 哺乳状況、離乳食の摂取状況
- 服薬時の反応
- 吐き戻しの有無
- 副作用の有無と程度
- 家族の発言、表情
TP
- 薬をごく少量の白湯で練って、団子状にして頬粘膜の内側に貼り付けるように置く
- 少量の白湯で溶いた薬を哺乳瓶の乳首に入れ、吸てつさせる
- 離乳食開始後の場合は、状況に応じて服薬ゼリーの使用も検討する
- 内服後に吐き戻した場合は「内服後何分経過したか」「どの程度戻したか」を確認し医師へ報告する
- 嘔吐の際は側臥位にし、吐物による窒息や誤嚥を防ぐ
- 空腹時に内服させる
EP
- 服薬の必要性と内服方法を指導する
- 服薬に関して不安や疑問があればいつでも伝えるよう指導する
幼児期
- 「苦くないよ」と噓をつくのは厳禁!家族や医療者への不信感につながる
- 遊びやご褒美を取り入れた楽しい雰囲気づくりを
- 褒める関わりが重要
OP
- 患児が薬をみた際の反応 (泣く、逃げる、怖がる など)
- 患児が内服する際の行動 (口を閉じる、口は開けるが飲み込まない など)
- 患児が好きなキャラクターや遊び
- 言葉への理解度
- 副作用の有無と程度
TP
- 服薬ゼリーやアイスクリームなど、患児の好きな食品を活用する
- 服薬方法の選択肢を説明し、選んでもらう
- スプーン、スポイト、シリンジを用意し、いくつかの方法で試してみる
- 声かけを工夫する 「お薬を飲むと元気になれるよ」「お薬を飲んだらシールを貼ろうね」
- 患児が好きなキャラクターや遊びを取り入れ、楽しい雰囲気をつくる
- 「お医者さんごっこ」を取り入れ、服薬への抵抗を軽減させる
- 看護師がいない方が落ち着ける場合は、保護者へ服薬介助を依頼する
- 吐き戻した際は、飲み直しの必要性を医師へ確認する
EP
- 保護者に、患児が楽しみながら服薬できる方法を提案する
- 保護者に「なんで飲めないの!」「ちっくんしてもらうよ!」など、怒ったり、脅したりすることがないよう伝える
- 服薬補助食品の選び方と使用方法について指導する
- 薬剤師に、より専門的な指導を依頼する
学童期
- 自主性を尊重する
- 作用や副作用、必要性などについて患児が納得し理解できるよう説明する
OP
- 服薬時の反応
- 服薬への思いや態度
- 服薬の必要性への理解度と意欲
- 副作用の有無と程度
TP
- 服薬への思いを聞き、寄り添う
- 服薬が苦手な理由を聞き、飲みやすくするための方法をともに考える
- 形状の変更が可能な薬剤であれば、医師に変更を依頼する(散剤→錠剤、錠剤→散剤など)
EP
- 薬の作用や副作用についてわかりやすく説明する
- 服薬の必要性について指導する
- 服薬に関してわからないことがあればいつでも聞いてよいことを伝える
- 自分で服薬する習慣の大切さを伝え、達成感を得られる方法を提案する
- ご家族へ、患児の主体性を尊重する重要性について指導する
小児の服薬管理は、こどもに合わせた方法で実施しよう
今回は、小児の服薬管理について、アプローチのコツや看護計画をとおしてご紹介しました。
小児の服薬管理においては、発達段階や患児の性格に応じて異なるアプローチが求められます。
- 乳児期のポイントは「保護者への指導」「安心感の提供」
- 幼児期のポイントは「楽しい雰囲気づくり」「認める関わり」
- 学童期のポイントは「服薬への理解を促し、自主性をサポートする」
患児に合った服薬方法を見つけられれば、服薬への抵抗を減らしたり、本人やご家族の負担を軽減したりできます。
小さな工夫の積み重ねが、こどもやご家族を支える大きな力となります。
ぜひ、現場で活用してみてください。

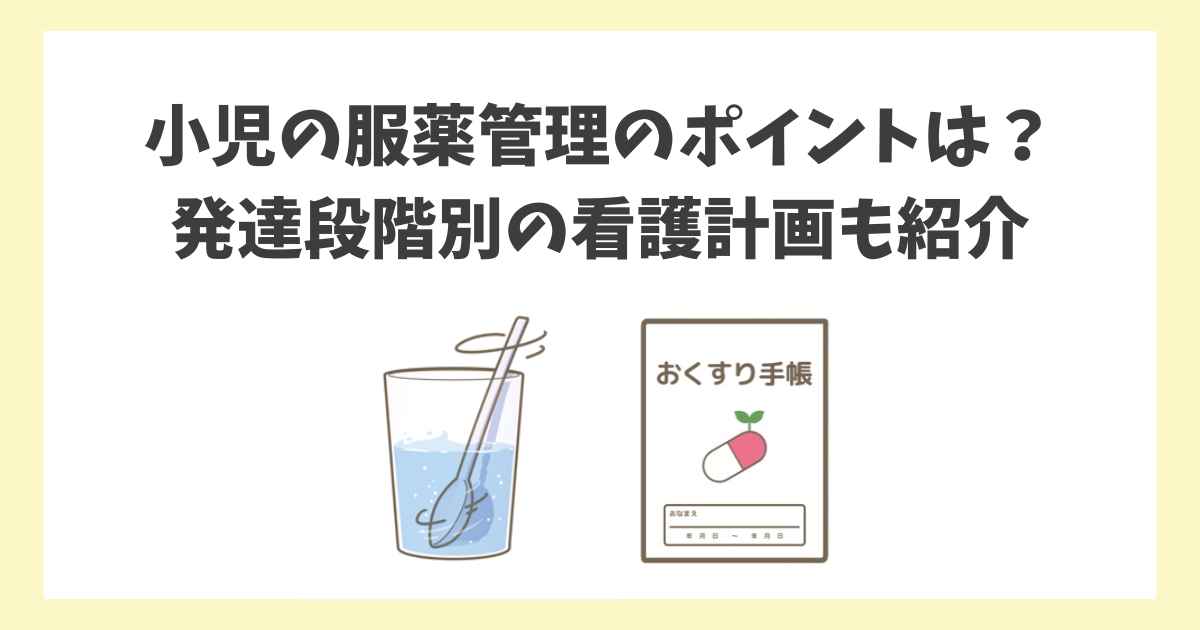
コメント