川崎病は、4歳以下の子どもに多く発症する、急性熱性疾患です。全身の血管に炎症が起こることで、さまざまな症状を呈します。
小児科病棟でもしばしば川崎病の患児に出会いますが、実習や勤務などではじめて受け持つ際は[病態や治療、看護計画についてよくわからない」という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、川崎病の病態生理、検査、治療、看護のポイント、看護計画について、小児科経験10年の看護師が実際の経験を踏まえて具体的に解説します。
川崎病の患児と関わる方は、ぜひご覧ください。
川崎病の病態生理
川崎病は、1967年に日本の川崎博士によって発見された疾患であり、博士の名から「川崎病」という病名が付けられました。
全身の血管炎が特徴であり、炎症が冠動脈に及ぶと「冠動脈拡張」や「冠動脈瘤」といった合併症を起こすことがあります。
原因は不明ですが、 が関わっている可能性があると考えられています。
4歳以下の子どもに多く発症しますが、とりわけ1歳前後の子どもの発症が多くみられます。
- 原因不明の全身性血管炎
- 4歳以下の子どもに多い とくに1歳前後の子どもに多い
- 冠動脈拡張、冠動脈瘤などの合併症が起こる可能性がある
川崎病の病態生理
全身性の血管炎は、何らかの原因によって免疫反応が過剰になった結果、炎症反応が上昇することで起こります。炎症反応の増加には「炎症性サイトカイン」が関与しており、全身の動脈に炎症を起こします。
なかでも、心臓の「冠動脈」に炎症が及びやすい特徴があるため、経過中に冠動脈拡張や冠動脈瘤が起こる可能性があるのです。
 ナースもも
ナースもも冠動脈とは、心筋に酸素や栄養分を届けるための血管です。
心臓の上に「かんむり」のような形で乗り、心臓を取り囲んでいます。
冠動脈に問題がなくても、発症後5年程度は外来通院が必要となることがほとんどです。一般的に予後は良好ですが、冠動脈病変が残った場合、その重症度によって治療や通院が必要となります。重症例では定期的な心臓カテーテル検査や、成人期以降にも通院が必要になることがあります。
川崎病の症状
川崎病では、全身の血管炎に伴った症状が出現します。基本的な症状は、以下のとおりです。
- 5日以上続く発熱
- 眼球結膜の充血
- 口唇の発赤(口唇紅潮、いちご舌)
- 不定形発疹(BCG接種部位の発赤)
- 頸部リンパ節腫脹
- 四肢末梢の変化(急性期:硬性浮腫 回復期:四肢末梢の膜様落屑)
川崎病の確定診断は、これらの症状のうち5つ以上に該当した場合にされます。しかし、該当する症状が5つ以下であっても、他の疾患が否定でき、血液検査や心エコーの結果などから川崎病と診断されることもあります。このようなケースは「不全型川崎病」とよびます。
発熱し始めてからすぐにすべての症状が出現するのではなく、日単位での経過中に徐々に症状が揃います。風邪や胃腸炎の症状がないのになぜか熱が下がらないし機嫌が悪い」という主訴で救急外来を受診され「川崎病」と診断されるケースが少なくありません。



主症状は必ず覚えておきましょう。国家試験にも頻出です。
「硬性浮腫(こうせいふしゅ)」とは、皮膚や周辺組織が硬くむくんだ状態です。普通の浮腫と比較して、圧迫しても痕がつきにくいのが特徴です。
川崎病の検査と診断
川崎病が疑われる場合や、川崎病と診断された場合には、採血や心エコー、必要に応じて心電図・胸部X線検査・尿検査などをおこないます。
血液検査データで注目すべき項目は以下のとおりです。
- 白血球数の増加
- CRPの増加
- 赤血球沈降速度の促進
- AST、ALTの上昇(初期)
- Alb、Naの低下(初期)
- 血小板増多(回復期) など
心エコーでは冠動脈の機能や心嚢水貯留の有無などについて確認します。
診断基準は、以下のリンクに詳しく記載されているため、参考にしてください。
日本川崎病協会「川崎病診断の手引き 改定第6版」
川崎病の治療
川崎病では、炎症を抑える治療と、抗血栓療法をおこないます。



急性期は、冠動脈病変が起こらないようにするために、とにかく炎症の抑制が重要です。
炎症の抑制
急性期には、抗炎症療法を実施します。基本の治療は以下のとおりです。
- IVIG(免疫グロブリン)
- 非ステロイド性抗炎症薬
IVIG不応例に対しては、IVIGの追加投与や、ステロイドパルス療法、血漿交換、免疫抑制剤などの治療が必要になることもあります。
IVIGは血液製剤であり、管理に注意が必要です。
参考リンク:独立行政法人医薬品医療機器総合機構「献血ヴェノグロブリンに関する資料」
抗血栓療法
川崎病では回復期頃より血小板の凝集がおこるため、抗血栓療法をおこないます。冠動脈部の血栓形成や心筋梗塞を予防する目的で、重要な治療です。
原則として、急性期から内服をはじめ、冠動脈病変がみられない場合でも発症後数ヶ月間にわたる内服が必要となります。
冠動脈病変がある場合はさらに長期に渡る内服が必要であり、巨大な冠動脈瘤が形成されたケースでは「ワーファリン」の内服が必要になることもあります。
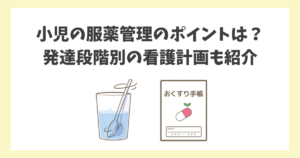
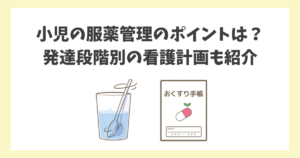
川崎病の看護のポイント
川崎病の看護のポイントについて、急性期と回復期に分けてそれぞれ解説します。
急性期の看護
急性期の看護のポイントは、以下の3点です。
- 薬剤の確実な投与
- 発熱や諸症状による苦痛の緩和
- 薬剤の副作用や、冠動脈病変による異常サインの早期発見
- 不安やストレスの軽減
重要なポイントを、表にまとめました。
| 投薬 | ・医師の指示を確認し確実に投与する ・点滴管理を徹底する ・IVIG投与時は、心電図とSpO2モニターを装着する ・アスピリンまたはフロベンの内服のサポート |
| 苦痛の緩和 | ・クーリングをおこなう ・発汗が多いため、清拭と保湿によって皮膚を保護する ・川崎病の症状の経時的変化を注意深く観察する ・可能な範囲で水分と食事の摂取を促す |
| 副作用や合併症の早期発見 | ・IVIGやアスピリン(フロベン)の副作用を把握し、異常所見の出現がないか注意する ・冠動脈病変がある場合、不整脈やST-Tの変化などがみられる |
| 不安・ストレスの軽減 | ・ベッド上での遊びの工夫 ・家族の精神的なケア ・休息の時間を確保する ・採血や心エコーなど検査時のストレスを緩和する |
重要なポイントについて説明します。
- 川崎病好発年齢である1歳前後の乳幼児では、血管が細く、点滴が漏れやすい可能性があります。点滴のすすみや、刺入部の観察を十分におこないましょう。
- IVIGの副作用にアナフィラキシーショックが報告されています。投与開始後1時間までに起こることが多い傾向にあるため、投与開始時は心電図・SpO2モニターを装着し、しばらくベッドサイドで見守りましょう。
- 内服が苦手な患児も少なくありません。入院中から退院後まで、少なくとも数ヶ月間は内服が必要であるため、患児や家族の負担を軽減しつつ、確実に服薬できるよう支援しましょう。
- 解熱剤の投与は禁止となることが多いため、クーリングをおこないましょう。
- 発熱や疼痛により飲水や食事摂取がすすみにくいことがあります。口当たりがよく、患児が好きなジュースやアイスクリームなどの摂取を、医師の指示のもとで検討しましょう。
- 家族は、入院前から患児の看病に疲弊していることが多く、患児が不機嫌なことや、入院・治療・予後への不安などから、身体的・精神的にストレスが溜まりやすい状況です。家族看護の視点を持ち、アプローチしましょう。



解熱剤が禁止となるのは、熱型の観察ができなくなるため。病状の把握のために、熱型の観察が重要なのです。
回復期の看護
治療効果が得られ、解熱および急性期症状の軽減がみられてくると、回復期に以降します。
回復期の看護のポイントは、以下の4点です。
- 冠動脈病変に関連した異常の早期発見
- 内服のサポートと副作用の早期発見
- 回復期症状である「膜様落屑」「口唇の亀裂・乾燥」のケア
- 退院指導
- ストレスの軽減
それぞれの詳細を、表にまとめました。
| 冠動脈病変に関連した異常の早期発見 | 回復期から血小板の凝集が起こるため、冠動脈病変が形成されることがある。循環器系の変化に注意する |
| 内服のサポートと副作用の早期発見 | 抗血栓療法により易出血状態となりやすい。安静度の拡大に伴う転倒や転落に注意する |
| 回復期症状である「膜様落屑」「口唇の亀裂・乾燥」のケア | ・指趾の落屑はめくらないよう注意する ・口唇の乾燥や亀裂が目立つ場合はワセリンやリップクリームで保湿する ・シャワー浴もしくは入浴により皮膚を清潔に保つ |
| 退院指導 | 退院後の服薬の必要性や、抗血栓療法によるリスクと対処、通院管理について指導する |
| ストレスの軽減 | 入院日数が増えることや、繰り返される検査などによってストレスが溜まりがち。プレイルームや病棟内での遊びを工夫する |
膜様落屑や口唇の皮は、気になってめくってしまうとそこから出血するリスクがあります。皮膚を保護し、めくらないよう指導しましょう。
退院指導は計画的にすすめ、入院による患児や家族へのストレス管理にも目を向け、総合的なケアを提供しましょう。
退院後の生活について不安や疑問があれば、必要に応じて医師や薬剤師と連携しながら解消していく必要があります。
川崎病の看護計画
1歳の川崎病患児を想定し、看護計画を立案してみましょう。
今回は、以下の看護問題をあげました。
- 川崎病症状や発熱による苦痛がある
- 冠動脈病変が起こるリスクがある
- 薬物による副作用が出現するリスクがある
- 服薬や通院の継続性について家族が管理する必要がある
- 点滴留置にともなうトラブルのリスクがある
- 入院や処置に対するストレスがある
これらのなかから、今回は太字で示した4つの看護問題について解説します。
服薬管理、発熱、脱水などに関する看護計画は、下の記事もあわせてご覧ください。
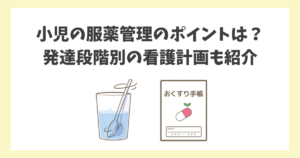
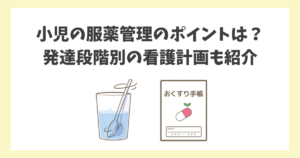
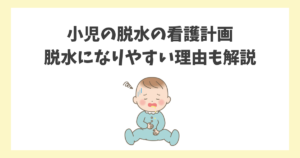
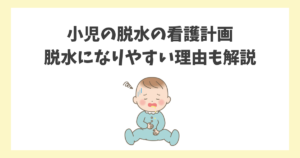
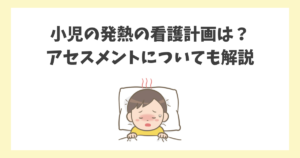
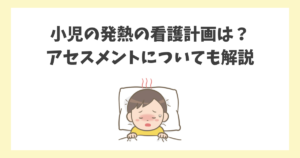
川崎病症状や発熱による苦痛がある
看護目標
症状による苦痛が軽減し、笑顔がみられる
OP(観察)
- バイタルサイン、熱型
- 川崎病の主症状の有無と程度(両側眼瞼結膜・口唇の変化・不定型発疹・頸部リンパ節腫脹・四肢末梢の変化)
- 機嫌、活気
- 水分摂取量
- 食事摂取量
- 睡眠の状態
- 脱水症状の有無と程度
- 排尿回数、尿量
- 排便回数、便性状
- 血液検査データ
TP(ケア)
- 発熱時はクーリングをおこなう
- 全身清拭・陰部洗浄をおこない皮膚の清潔を保持する
- 可能な範囲で飲水を促す
- 睡眠時間を確保できるよう、ケアのタイミングを工夫し、夜間は物音に注意する
- 口唇の乾燥や亀裂があれば、ワセリンやリップクリームで保護する
- 点滴管理をおこなう
- 口腔ケアをおこなう
- 手足の爪を切り、清潔に保つ
EP(教育)
- 頻回なバイタルサイン測定が必要になることを伝え、理解を得る
- 安静の必要性について説明し理解を得る
- 飲みやすいものや食べやすいものを摂取するよう指導する
- 検査の必要性について医師から説明してもらう
冠動脈病変が起こるリスクがある
看護目標
異常が早期発見され、適切な処置を受けられる
OP(観察)
- バイタルサイン
- 心電図波形(PR・QT延長、異常Q波、ST-Tの変化、リズム不整)
- 心音
- 機嫌、活気
- 顔色
- 心エコーの結果
- 胸部X線検査の結果
- 強い腹痛、悪心・嘔吐、呼吸困難、突然の啼泣、顔色不良:動脈瘤による心筋梗塞が生じているリスクあり
TP(ケア)
- バイタルサインと心電図をモニタリングし、異常時はすぐに医師へ報告する
- 検査が予定通りおこなわれるようサポートする
- 顔色不良や呼吸困難感が出現した際はすぐに他のスタッフへ応援を要請し、救急カートとDCを準備する
EP(教育)
- バイタルサイン測定や心電図モニター装着の必要性について説明し理解を得る
- 家族に、いつもと違う様子があればすぐに知らせるよう指導する
薬物による副作用が出現するリスクがある
看護目標
副作用が早期に発見され、適切な処置を受けられる
OP(観察)
- 各薬物による副作用の有無と程度(詳細は下部表参照)
- バイタルサイン
- 心電図、SpO2モニター値
- アナフィラキシーショックの既往
- アレルギーの既往
- 異常な発汗の有無
| 薬剤名 | 副作用 |
| IVIG(献血ヴェノグロブリン) | ・アナフィラキシーショック ・肝機能障害(黄疸、 ・無菌性髄膜炎 など |
| アスピリン | ・出血傾向 ・肝機能低下 など |
| ステロイド | ・ムーンフェイス ・食欲亢進 ・血圧上昇 など |
TP(ケア)
- IVIG投与開始前と投与開始後でバイタルサインの変化を観察する
- IVIG投与中は医師の指示に従いバイタルサイン測定をおこなう
- ショックが疑われる場合、ただちに医師を呼び、救急カートや酸素投与の準備をおこなう
- 出血時はバイタルサインを測定した後医師へ報告する
- 口腔ケアは力を入れずやさしくおこなう



出血は、口や鼻に起きることが多いです。
気が付いたら鼻血(医療用語では鼻出血)が出ていたということもあるため、注意して観察しましょう。
EP(教育)
- バイタルサインやモニタリングの必要性について説明し理解を得る
- 患児に何か異変があればすぐにナースコールで知らせてもらう
- 出血時はすぐに看護師に知らせてもらう
服薬や通院の継続性について家族が管理する必要がある
看護目標
家族が川崎病とその治療、退院後の生活について理解でき、自分の言葉で説明できる
OP(観察)
- 家族の発言、表情
- 服薬時の患児への関わり方
- 服薬・検査・通院への理解度
TP(ケア)
- 治療や生活などについて疑問や不安があればいつでも看護師や医師へ話してよいことを伝える
- 服薬方法や退院後の管理方法について一緒に考える
EP(教育)
- 服薬・通院の継続の必要性を説明し理解を得る
- 服薬の方法を指導する
- 薬剤の用法・用量や副作用について、薬剤師に専門的な指導を依頼する
- 退院後の生活の注意点について説明する
- 冠動脈病変の存在による運動制限がある場合は、退院後の生活でも守れるよう指導する
- IVIG投与後の予防接種は、発病から



アスピリン製剤服用中は、出血傾向がみられます。退院後も転倒・転落に引き続き注意してもらうことが重要です。
まとめ
この記事では、川崎病の看護について解説し、具体的な看護計画についてもご紹介しました。
川崎病の看護では「急性期」「回復期」それぞれでポイントや視点が異なる部分があります。病状を理解し、その状況に合った看護の提供をこころがけましょう。
参考文献
- 中央法規「シリーズナーシングロードマップ 疾患別小児看護 基礎知識・関連図と実践事例」初版第4刷
- 照林社「母性・小児看護ぜんぶガイド」第2刷
- 国立研究開発法人国立成育医療研究センター「川崎病」
- 一般社団法人日本川崎病学会「川崎病診断の手引き改定第6版」


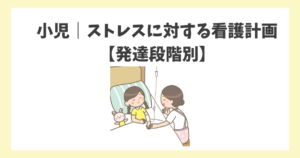


コメント