子どもは、環境の変化や家族との分離、生活リズムの乱れなど、さまざまな要因でストレスを感じています。しかし、大人のように気持ちや考えをうまく言語化するのが難しく、不安や情緒の不安定さ、ときには身体症状として現れることもあります。
とくに、病院という慣れない環境では、疾患や治療にともなう身体的な苦痛、生活の変化や医療者の存在、家族との分離にともなう精神的な苦痛を強く感じ、治療やケアへの適応が難しくなることもめずらしくありません。
そのため、看護師は子どものストレスサインをいち早く察知し、適切な看護を提供することが大切です。
この記事では、入院中の小児がストレスを感じる原因と影響について解説し、現場で実践できる看護計画や具体的なケアのポイントについて解説します。
小児看護に携わる方はもちろん、小児科実習を控えた看護学生の方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
 ナースもも
ナースもも今回の記事は、小児専門病院での長年にわたる勤務の経験を振り返りながら、経験ベースで書いています。ご理解ください。
小児が入院中にストレスを感じる主な原因
小児が入院中に感じるストレスの原因はさまざまですが、ここではとくに影響が大きいと考えられる以下の4つについて解説します。
- 慣れない入院生活によるストレス
- 疾患・検査・治療による身体的ストレス
- 理解できない状況への不安【年少児】
- 先の見通しが立たない不安【年長児】
順にみていきましょう。
慣れない入院生活によるストレス
入院生活では、以下のようなことが生じます。
- 遊びや運動が制限される
- 登園や通学ができなくなる
- 友達と会えなくなる
- 家族との時間が少なくなる
- 医療者と関わる時間が多い
- 生活リズムが変化する
病院での生活は、自宅での日常生活とは大きく異なります。病室という限られた空間で過ごし、自由に動くこともできず、普段の遊びや活動が維持できないことがストレスの原因になります。
また、看護師や医師などの医療スタッフが常に関わる環境も、小児にとって緊張が高まり、心身ともに負担を感じやすくなる原因のひとつです。
食事や睡眠の時間が普段と異なることも、小児にとって大きな負担であるといえます。
疾患・検査・治療による身体的ストレス
疾患・検査・治療による身体的ストレスの具体例には以下のようなものがあります。
- 発熱、疼痛、嘔気、嘔吐、下痢、倦怠感、呼吸苦などの症状による苦痛
- 採血、点滴、手術などの処置や治療にともなう痛みや不快感
- モニター、点滴、ドレーンなどが体につながっていることへの苦痛
症状がなかなか改善しないことによる治療意欲の低下や、痛い思いをした検査や処置の拒否がみられることもめずらしくありません。
理解できない状況への不安【年少児】
年少児は、入院の意味や治療の必要性を理解するのが難しく、「なぜここにいるのか」「なぜ怖い人がたくさん来るのか」「なぜ痛いことをされるのか」がわからないまま、ただただ怖い思いをすることになります。
また、年少になればなるほど分離不安が強く、家族がそばにいない状況ではストレスをより強く感じるでしょう。
先の見通しが立たない不安【年長児】
年長児が感じるストレスの具体例は以下のとおりです。
- 退院の見通しがわからない
- 病状への不安
- 入院生活の決まりに対するストレス
年長児になるにつれ入院や治療の目的をある理解できるようになるものの、それと同時に「いつ退院できるのか」「治療はいつ終わるのか」など、先の見通しが立たない不安がストレスの原因となります。
入院によるストレスが小児に及ぼす影響【発達段階別】


入院によるストレスは、小児の心身にさまざまな影響を及ぼします。ストレスサインの現れ方は発達段階によって異なることを理解しておきましょう。
ここでは、乳児期・幼児前期・幼児後期・学童期の4つに分けて、それぞれの発達課題に触れながら、詳しく解説します。
乳児期(1歳まで):環境の変化と母子分離が大きなストレスに
- エリクソンの発達課題は「基本的信頼 vs 不信」
- 「愛着形成」重要他者(特に母)への基本的な信頼感を獲得する
- 「人見知り」生後6~7か月頃になると両親を認識でき、それ以外の人への人見知りが始まる
この時期の子どもは、母との安定した関わりを「安全基地」と捉えます。そのため、入院によって母との分離が増えると、安心感を得る機会が減り、基本的信頼感の発達が妨げられてしまうのです。
親しい人とそうでない人の区別がはじまると、分離不安による情緒的な反応サインとして現れやすくなり、食欲低下や不眠などに加え、発熱、嘔吐、下痢などの身体症状が出現することもあります。
幼児前期(1歳~3歳まで):母子分離への不安がもっとも強い時期
- エリクソンの発達課題は「自律性 vs 恥・疑惑」
- 自己中心性の思考
- 重要他者への愛着行動は2~3歳ころまで続く
- 重要他者が安全基地として確認されることで、次の探索行動に向かうことができる
この時期の子どもには「自分でやってみたい」という気持ちが芽生え、「自分で決める」「自分で遊ぶ」ことに喜びを感じます。よって、入院による遊びや行動の制限は、大きなストレス源となるのです。
また、母子分離不安がとくに強い時期であり、不安をコントロールすることができません。母がそばにいないと泣き続けたり、一緒に過ごす時間が普段より少し短くなっただけでも、夜泣きが増えたりすることがあります。
幼児後期(4歳~6歳まで):病院や医療者への警戒心や恐怖心が強まる時期
- エリクソンの発達課題は「自主性 vs 罪悪感」
- 自分が重要他者と異なる存在であることを自覚すると第一次反抗期が現れる
- 3歳ころには重要他者と自分が異なる存在であることを認められるようになる
- 愛着形成が十分であれば、基本的生活習慣を自主的に実施するようになる
- 好奇心旺盛
- 集中力が伸びていく
幼児後期には好奇心がよりいっそう旺盛になり、周囲のものやできごとに対して「どうして?」「なぜ?」と疑問や興味をもつようになります。
入院していること、症状、医療行為などに対して「どうして?」と疑問を抱きますが、説明を聞いても十分に理解できるところには達しません。そのギャップが、この時期の子どもを苦しめることになるのです。
また、医療行為や処置に対する恐怖心が強まるのもこの時期です。「自分が悪いことをしたから注射をされたんだ」と思いこんだり、緊張や怖さのあまりに暴れたり、逃げたりすることがあります。
指しゃぶりや夜尿など、何らかの退行現象が現れることもめずらしくはありません。
そして、入院生活に慣れてきた頃や医療介入が減少していった先にも「看護師さんが会いに来てくれなくなった」「一緒に遊ぶ人がいない」などと、孤独感を感じることがあります。
学童期(7歳~12歳まで):先の見通しが立たないことがストレスに
- エリクソンの発達課題は「勤勉性 vs 劣等感」
- 「怒り」「恐怖」「嫉妬」「愛情」「喜び」を感じるようになる
- 学年が進むにつれ仲間意識が高まる
- 具体的な思考かた抽象的な思考へすすむ
学童期は、友達や学校の先生など、家庭外での人との結びつきが重要な時期です。この時期に入院を余儀なくされると、友達との分離の辛さ、学校へ通えないことへの焦りや劣等感などを感じやすくなります。
また、病状や治療について自分で考えられるようになるあまり、想像から不安や恐怖が発生しやすくなるのも学童期にみられる特徴です。
そして、「治療=受け身」の状態もまた、ストレスを感じる一因です。「自分でやりたい」「自分で考えたい」という気持ちが強いのにも関わらず、治療方針が医師や親によって決められていうことにストレスを覚えることもあるでしょう。
小児のストレスに対する看護のポイントと看護計画【発達段階別】
ここからは、小児のストレスに対する看護のポイントと看護計画について、発達段階別に解説します。看護問題は共通で「入院生活による不安やストレスがある」とします。
乳児期
- 安心できる環境づくり
- 母子分離を最小限に
看護目標
安心できる環境の中で過ごすことができる
母乳やミルク、離乳食を5割以上摂取でき、睡眠を確保できる
OP(観察)
- 機嫌
- 表情
- 活気
- 泣き続ける様子があるか
- 睡眠時間と睡眠パターン
- 食事・水分摂取状況
- 排尿・排便回数と性状
- 嘔気・嘔吐の有無
TP(ケア)
- 可能な限り母または主要な養育者の付き添いを促す
- 母不在時は看護師が抱っこや優しい話しかけなどによりスキンシップを図る
- 普段から使用しているタオルやぬいぐるみ、おしゃぶりなどを持ち込み、安心感をあたえる
- 温度や湿度、照明を調整し、患児が安心できる環境を整える
EP(教育)
- 付き添いの重要性と、可能な範囲での関わり方のポイントについて説明する
- 母子分離不安の影響について説明し、母が必要以上に不安を抱かないようにする
- 患児の安心につながるようなものやおもちゃの準備を依頼する
幼児期
- 選択肢を与え自主性を尊重する 例 「お熱図る?それとももしもちを先にする?」
- 好きな遊びやキャラクターを取り入れる
- 母子分離を最低限に
- わかりやすい言葉で説明する
- 表情やしぐさを見逃さない
看護目標
食事摂取量と睡眠状況が安定し、笑顔がみられる
適切なサポートを受けながら医療処置に協力できる
OP(観察)
- 表情
- 発言
- 機嫌
- 活気
- かんしゃく、夜泣き、赤ちゃん返りなどの行動変化
- 食欲
- 水分・食事摂取状況
- 睡眠時間と睡眠パターン
- 医療行為に対する反応
- 看護師や医師に対する警戒心の程度
- 好きなキャラクターや遊び
TP(ケア)
- 可能な限り母または父の付き添いを確保する
- 「検温」「回診」「食事」「清潔ケア」などのタイミングを一定にし、次の行動を予測できる環境をつくる
- 患児本人に選択肢を与え、自主性を尊重する
- 積極的に遊びを取り入れ、安心感を与える
- 処置の際は「何をするのか」「どうすれば痛く感じにくいか」についてわかりやすく説明する
- 好きなキャラクターのご褒美シールやスタンプを活用し、処置への協力を促す
- 思いや気持ちを表出する機会を設ける
EP(教育)
- 保護者に対し、幼児期の母子分離不安とその対処法について説明する
- 保護者の不在時に患児が安心できる工夫について伝え、協力を促す
- 医療行為に対し「痛くないよ」「へっちゃらだよね?」などといった声かけを控えてもらい、寄り添う姿勢を大切にするよう指導する
- 患児が泣いているときに叱らないよう指導する
- 適度な恐怖を与えないため、医療行為をおどし文句として使わないよう指導する



親御さんのなかには「悪いことしたら先生に注射してもらうよ」「もう年少さんなんだから泣かずにやりなさい」と言う方もいます。これでは、患児の不安は強まるばかりです。
学童期
- 治療方針、退院時期、毎日のスケジュールなどについて見通しを立てて説明する
- 自主性、主体性を尊重する
- 家族、友人との時間を確保する
- 学習の機会を確保する
看護目標
入院や治療について理解し、自分の言葉で説明できる
家族や友人と関わる時間が確保される
学習の時間が確保される
OP(観察)
- 入院期間や治療内容への理解度
- 表情
- 発言
- 入院中の生活リズム
- 学習状況
TP(ケア)
- 医師へ、治療スケジュールや退院の見通しに関する説明を依頼する
- 検査や処置など、あらかじめ決まっている予定は早めに患児へ伝える
- 患児の不安や恐怖を受け止め、寄り添う時間を設ける
- 処置や検査の前には、その内容や方法について年齢に応じた言葉で説明する
- 院内学級やオンライン学習などを活用し、学習の機会を設ける
- 可能な範囲で友人との連絡手段を提供し、社会とのつながりを意識できるよう支援する
- 体温測定や服薬管理など、患児が治療に対し主体的に関わる機会を設け、自主性を尊重する
EP(教育)
- 家族や友人との面会やオンライン通話などによる関わりの重要性を説明し、協力を促す
- 患児が疾患や治療について理解しやすいよう、説明の仕方を一緒に考える
- 学習支援の活用について情報提供する
- 強がっているようにみえて実は寂しい思いをしている可能性があることを伝え、可能な範囲で付き添いや面会を依頼する



いつも笑顔で頑張っている患児が、実は隠れて涙を流しているという場面を経験したことがあります。勉強のノートに「いつ退院できるの」と書いていた患児もいました。サインを見逃さないことが大切!
まとめ
この記事では、入院中の患児へのストレスの概要や、看護計画について解説しました。
ポイントをおさらいしましょう。
- ストレスの感じ方は発達段階によって異なる
- 乳児期では、母子分離が大きなストレスとなる
- 幼児期では、母子分離によるストレスに加え、医療行為や遊びの制限にともなう苦痛がある
- 学童期には、友人との関わりや学習の制限、治療や入院に関する見通しが立たないことがストレスとなる
ただし、これらはあくまでもひとつの目安です。発達段階だけでなく、患児一人ひとり、それぞれ違った感じ方や考え方をしています。
患児や家族とじっくり関わる時間を設け、さまざまな部分に現れる「ストレスのサイン」を見逃さすにキャッチしていきましょう。そして、個別性のある看護計画へ発展させてみてください。
参考文献
- 医学書院「専門分野Ⅱ小児看護学概論 小児臨床看護総論 小児看護学①」第11版第9刷

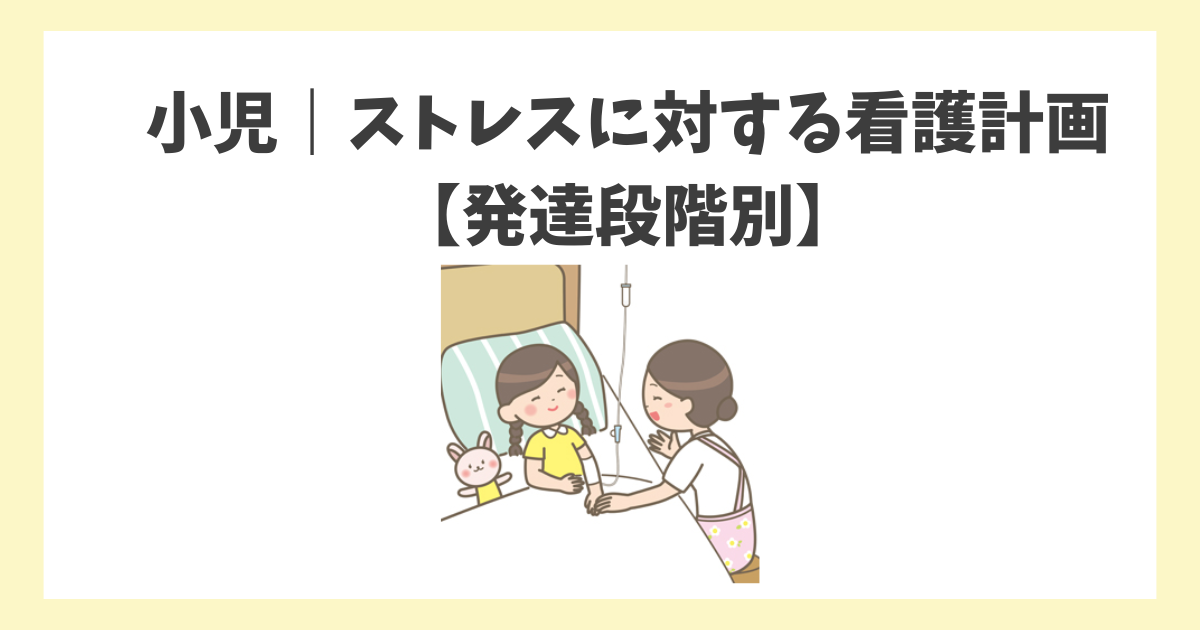
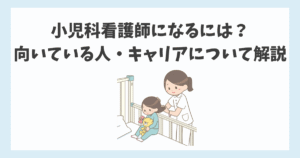
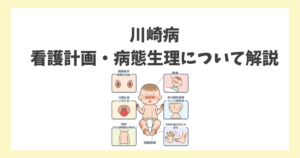
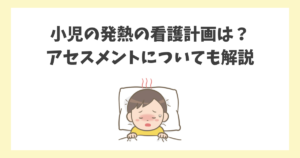

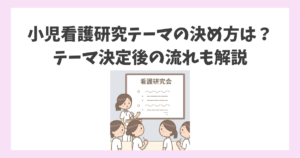
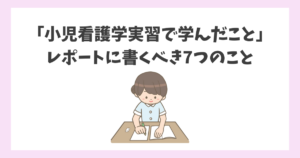
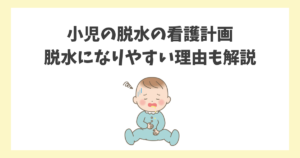

コメント